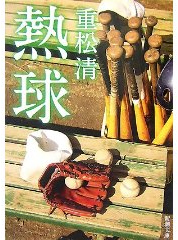◎熱球
◎熱 球
重松 清
徳間文庫
この『熱球』はタイトルからして、もう絶対に好きになる小説に違いないという予感があった。
…その予感はほぼ当たったといってもいい。
【甲子園に憧れていた。エースとして予選を勝ち進んだ。でも、決勝戦前夜の不祥事が僕と仲間たちの夢を断ち切った。20年後、38歳になった僕は一人娘を連れて故郷に帰ってきた。仲間と再会した。懐かしいグラウンドでは、後輩たちが、あの頃の僕らと同じように白球を追っていた。僕も、もう一度、人生のマウンドに立てるだろうか。】
38歳の「僕」の故郷への思いが痛いほど胸を突く物語だ。
しかし読者である私は「僕」よりもずっと歳を食ってしまっているし、故郷があるわけでも、妻子がいるわけでも、まして甲子園目指し白球を追いかけてきたという経験もない。主人公と共有する材料はないないづくしであるのだが、読み終えたときには間違いなく「僕」に共感していた。
最初に『口笛吹いて』を読み終えたときに「共有できなくとも共感できる小説」と書いたとおり、その印象のまま『熱球』まで継続している。正直に言えば、ないないづくしなだけに身につまされ度が少なかった分だけ、今までよりも物語に入りやすいとは思った。
私には友達に関して「こいつと野球をやったら楽しいか?」という選択基準がある。
別に野球が上手いとか下手だとか、歳が離れていようが、男女の違いすらどうでもよく、キャッチボールだけで時間を忘れさせてくれる相手ならば一生付き合っていける自信がある。
ましてグラブの皮革の香りが好きだったり、夏の甲子園大会の決勝戦が終わったときに、中継のエンディングにふと行く夏を惜しみながら、秋の気配を思うくらいの感性のある奴ならば最高だと勝手に決め付けている。
この『熱球』。例のごとく、重松清の小説の「僕」は東京での仕事を辞め、故郷に一人暮らしの父親を残して人生の岐路に立ち、八方塞りの状況に喘いではいる。しかし根底に野球小僧の熱い血が燻っている。乱暴な言い方だが、こういう主人公を擁した小説が嫌いになるはずはないのだ。
高校野球に関しては大半の三年生は夏に負けたら、そこで引退ということにドラマを感じる。そして夏の甲子園にはたった一校を除けばすべての高校球児が負けて終わっていくという不文律がある。
以下は少々自分の話を。
遠い日、高校一年の夏。私の母校の県予選大会はノーシードで、一回戦も無名の県立高校相手にようやく辛勝したというスタートだった。ところが六年後にドラゴンズの山本昌が入団する強豪・日大藤沢に劇的な逆転サヨナラホームランで勝利した辺りから勢いに乗り、準決勝ではノーヒットノーランでの勝利。本当に嘘みたいに甲子園のスコアボードが夢枕に現れ、浮き足だってしまった記憶がある。結果的には決勝戦の川崎球場で原辰徳の東海大相模に完膚なきまでに叩きのめされ、それは今でも苦々しい思い出として、テレビに原辰徳が映り、今の住処の近所にある東海大相模の正門を通りがかる度に、深酒の後のゲップのように生々しく不快感が蘇ってくるのだが、あれは私が唯一、愛校精神に目覚めた夏でもあった。
だが、この小説の「僕」のように県予選の決勝まで勝ち進んでおきながら、仲間の不祥事によって突然引退を宣告されてしまう場合もありえるのだろう。試合に負けることもなく舞台から下ろされてしまったことで味わう敗北とはいったいどういうものなのだろうか。
二十年ぶりに故郷に帰ってはみたものの、ここで骨を埋めるか、東京に戻るのか決めかねて周囲から非難される「僕」は、そこでかつての仲間たちと再会する。
定食屋を開店させたものの、泣かず飛ばずで借金まみれの不動の四番バッターだった亀山。母校の野球部の監督に就任したが、嫁と実家の不和に悩むバッテリーを組んだ相棒の神野。そして不祥事の当事者となり、故郷を追われトラックの運転手になった、かつてのアイドル的女子マネージャーの恭子。
出場辞退が突然言い渡された夜、「わしら、これで自動的に引退なんじゃけぇ」とナイン涙で最後のキャッチボールを始める場面。そういう記憶のひとつひとつが彼らの人生に暗い影を落としているのだが、この辺りの重松清の描写力と人物設定は本当に上手いと思った。
「逃げてはいけないと思い込んでいた。逃げなくてはどうしようもないことはたくさんある。臆病者や卑怯者と呼ばれようとも、逃げるしか道がないことは確かにある。僕たちは大人になってから何度逃げてきただろう。俺は一度もないぞと言う人がいたら、僕はふうんすごいですね、と感心して、決してその人と友だちにはならないだろう」
「僕」は故郷から逃げて、東京の大学を出て、東京で仕事を見つけ、東京で家庭を築き、気がつくと人生の半分以上は東京での暮らしとなってしまったとき、改めて故郷とかつての仲間との再会する。
そして“熱球”とマジックで書かれた硬式ボールを握り締めながら、「逃げてもいいんだ」という思いに気がつく。
『熱球』は、試合で負けることも許されないまま敗北した主人公が、その場所に立ち帰ることで、ようやくきっちりと負けることが出来た物語なのかもしれない。
…高校球児たちのように。
a:3158 t:1 y:2