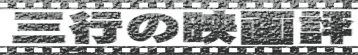2003年深作映画

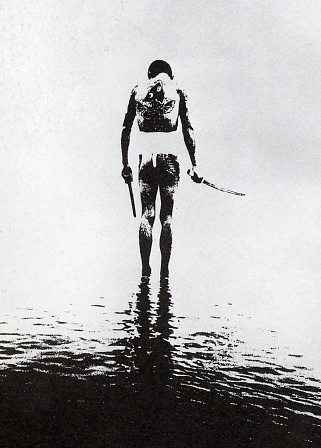
現在、2008年3月。
もうなにもかも十年遅かったことはわかっている。
私が四十手前であるならば、深作欣二をもっと熱く語れたに違いない。残念ながら十年前にはホームページの何たるかも知らなかった。
もう懐かしさも過ぎて、少しづつ記憶から記録へと移行しつつある。
今や「名画座」といっても死語かも知れない。
私は70年代の半ばから80年代の前半にかけて名画座と呼ばれる小さな映画館に通いつめていた。
もうふた昔以上も前の話だ。
そこでも概ね十年のズレで時代を追体験してきたわけである。
当時はロードショー館の前売りで1200円くらいだったと思うが、名画座は3本立て300円から500円くらいで、ちょっとした繁華街に行けば絵看板の小屋を見つけることが出来た。
思えば私が名画座に足しげく通っていた時代がすでに映画興行は斜陽産業の象徴であり、古くからの筋金入りの映画狂にいわせれば、私の世代が名画座の最後の生き残りなのかも知れない。
浅草の東京クラブや渋谷の全線座という有名な名画座が次々と閉鎖していく渦中にあり、多くの名画座がポルノやピンク映画の常打ち小屋になっており、すでに末期症状の様相を呈していた。
どこの小屋も老朽化が激しく、臭くて不潔で陰気という形容詞が当てはまり、いつもガラガラで、繁華街の一等地に建物を構えていることが奇跡のような存在。
時代は間もなくバブル景気に入り、存在すること自体が許されなかったかのように、次々と取り壊されて、いっときの夢の中で遊んだ名画座の殆どが跡形もなく消えてしまった。
そんな名画座で深作欣二のフィルモグラフィの大半を観た。
『仁義なき戦い』や『仁義の墓場』を観ている瞬間、瞬間が「人生、最良の日」だった。
その深作さんが亡くなってからも既に五年が経過している。
やはり今ここで深作映画を語るには私は無自覚にも歳をとりすぎた。『仁義なき戦い』公開当時の深作欣二は43歳。脚本の笠原和夫で46歳。
菅原文太40歳、梅宮辰夫35歳、松方弘樹31歳、北大路欣也30歳、千葉真一34歳、渡瀬恒彦29歳、小林旭38歳。山守親分こと金信雄ですら50歳の若さ。
改めて彼らの仕事の凄さにも驚愕するが、何とも暗澹たる気分になってくる。やはり十年遅かった。
今、ここで深作欣二映画を追想したところで、どれだけの意味があるのか。頑張ればやれないこともないのだが、それをすることで今の自分に跳ね返ってくるダメージを考えるとしんどい。
幸い(?)深作欣二の訃報を機に以前の職場を辞め、半年間浪人していた2003年に追悼の上映会として渋谷東映での『仁義なき戦い』のオールナイト、ならびに千石の三百人劇場での「深作欣二追悼特集〜まだピリオドは打てない」から遺作とされる『バトル・ロヤイヤル?』まで深作映画を続けて観賞した際の記述が残っていたため、ここに転載してみる。
おそらく2008年の現在から邂逅するよりも、訃報に直面した2003年当時の記録の方が、まだ私の深作欣二映画への思いが伝わるのではないかと思うからだ。
2003.2.8(土)渋谷東映
仁義なき戦い
1973東映/脚本:笠原和夫/出演:菅原文太/梅宮辰夫/松方弘樹/伊吹吾郎/渡瀬恒彦/川地民夫/田中邦衛/三上真一郎/渚まゆみ/名和宏/曽根晴美/金子信雄

『仁義なき戦い』5部作をオールナイトで一気に観た。
…って、おいおいその書き出しは高校生のときの映画鑑賞記録のまんまじゃねぇか!
ウソではない。1月12日、深作欣二さんが亡くなったのだ。思えば全盛期と比べて信じがたいほどに映画を観なくなってしまった現在であれ、曲がりなりにも20年もビデオソフト業界にいたのは、元を辿れば高校から浪人、大学と深作さんの映画に頭までどっぷりと浸かっていたからに他ならず、大学を卒業してからの大半の人間関係は深作さんがいなければ、まったく違うものになっていたはずである。
深作欣二が叩きつけた映像の数々は、私の脳中枢に組み込まれている。
かつて狂ったように深作映画を小汚い名画座で追いかけ回しては、熱い思いのままに鑑賞ノートを綴っていた日々のこと。
それは当時、小生意気にも評論文を気どっていたが、実はオマージュを延々と書き連ねたファンレターのようなものだった。
一度でいいから広島のアーケード街を絶叫して駆け抜けた一群に紛れてみたかった…と。
いつしか時は流れ、最初の10年は三角マークを戴いたビデオ会社でVTRにパッケージされた深作映画を売って歩き、後の10年はレンタルビデオ屋で深作映画を7泊380円で貸していた。
かつてノートに書き残した膨大な“深作欣二”という文字は発注書に書かれることになり、コンビューターのPOP文字に変換入力されていったのだ。
10年間勤めたビデオショップを売却し、一緒に働いてきたスタッフとの送別の席で突如「深作欣二、死去」の報を聞いた。店を失ったこと以上の喪失感だった。肉体の一部をむしり取られたような気がした。だが、不思議と悲しくはなかった。現実のものとして受け止められなかったからだろう。その後のTVのワイドショーで繰り返された無味乾燥とした追悼特集と、コメンテーターたちのとってつけたような付け焼き刃的なスタジオ・トークに鼻白みながら、永年の癖で“ふかさくきんじ”という音のみに過剰に反応してしまうという日々が続く。唯一、スポーツ紙に載っていた山田洋次の「同じ時代を生きた戦友を失った」という追悼コメントが涙腺を刺激した。
「“哀悼コーナー”は作らないのですか?」と職場でいわれたが、とてもそんな気にはなれなかった。築地本願寺での追悼会も行くことを勧められたが、それも違うと思った。有り体にいってしまえば、暗闇に身を沈めてドキドキしながらスクリーンと対峙していた青春時代への回顧に浸ることこそが哀悼の意としてふさわしいのではないだろうか。
深作欣二が再起不能の癌に冒されていることは週刊誌の記事で知っていた。だから最低限の覚悟は出来ていた。深作の闘病は、イコールで新作『バトル・ロワイヤル2』のクランクアップまで持つのかという形の報道もされた。前作の段階から全身を貫く激痛をモルヒネを打って撮影に臨んでいたことも知っている。ビートたけしが、深作演出についてインタービューされたとき、「若いのがバタバタ倒れているのに監督だけが走り回っていた(笑)。最初にこんな厳しい現場を見ていたら映画監督やっていたかどうかわかんないね。」
“深作組”は別名“深夜作業組”とスタッフに恐れられていた。
『バトル・ロワイヤル』のメイキングビデオでの70歳のエネルギュッシュな深作を見ていると、死は体力への過信と不摂生によるものだったとしても、出来れば完成までこぎつけて欲しかったという思いはある。思いはあるのだが、「あれほど元気だったのに信じられない」などという追悼の仕方は絶対に違う。深作欣二はリタイアしたまま物故記事に載せられる巨匠たちと違って、執念で撮影スタートまで持ち込んだのだ。これは部類の深作狂としても不思議に誇らしい気分であり、そのことが大きな救いとなった。
『仁義なき戦い』はもう何度観たかわからない(調べればわかるが)。オールナイト五部作一挙上映というのだけでも何度となく出かけていると思う。もちろん世間には相当な“仁義マニア”がいるので、この程度の観賞歴は大したことはないのかも知れない。ただ少なくとも首都圏ではここ10年、このような企画はなかったはずだ。そもそも、私が通いつめた殆どの映画館は消えてしまった。ビデオデッキとレンタルソフトの普及は、観客を暗がりの小屋から、お茶の間へと移動させた。
そして当時から相当に老朽化していた3本立て300円の名画座たちはバブル経済から平成不況へと流れていった都市部では存在そのものが許されるものではなかったのだろう。

20年もそれで食っていたにもかかわらず、あらゆる意味で映画をビデオで観ることがどうしても好きになれない。よくいわれる画面や音の迫力の違いではない。もともと比率の問題でいうならば劇場のスクリーンと、六畳間の25インチモニターにそれほど視覚範囲の差はない。暗闇が心地よければ部屋の明かりを消せばいいのだし、VHSの解像度の悪さもDVDならば、ある程度解消してくれるだろう。実際、画質の問題というならば、名画座で上映されていた使い回された限界寸前のフィルムのひどさといったらなかった。音とび、絵とびは当たり前。これがカラーかと思えるほど退色し、上映中にフィルムがきれて中断する、上下が入れ替わる、しかも映写室のオヤジが居眠りでもしているのか観客が怒鳴るまで気づかないなど日常茶飯事だった。
しかも東映やくざ映画や日活ロマンポルノの常打ち小屋ともなると、客筋は極端に悪く、自分も含めて煙草は吸い放題、酒は飲み放題、痰は吐き放題、鼾は掻き放題。便所のドアは開きっぱなしで小便の臭いが充満し、鉄道ガード下の小屋ともなると天井から容赦なく轟音と振動が襲ってくる。下手をするとネズミが這い回っていたことすらあった。
そんな環境のものが例外なく駅前の一等地にあったわけだから、淘汰されて当然といえば当然なのかも知れない。大概はスーパーやマンションになったり、立体駐車場と形を変えてしまった。
しかし、一般的に青春時代といわれる時期の大半を、私はそんな文化の最底辺な世界に身を沈めてきた。名画座の暗闇は明るい太陽とは無縁の世界ではあったが、微塵の後悔もしていない。当然の話、今やれといっても出来ないのだから…。
素晴らしいシーンでの感動、そうでなかったときの落胆を客席が一斉に共有する瞬間がある。劇場で映画を観る醍醐味はそこにある。ライブやプロレスではないが、ごく稀れに、観客の思いが妙な形で結集してしまい、その作品を実際以上に面白くさせてしまうことがある。そうなってくると共有ではなく共犯に近い。ビデオでは共犯意識の高みに昇ることはあり得ない。
『仁義なき戦い』は観客を共犯者にさせることで、限りなく昇りつめていく映画だ。
深作自身、キネマ旬報誌の対談でこのシリーズを称して“一種の祭”だと述べていたことを思い出す。熱気ムンムンの場内で、男たちの欲望と流血のドラマに興奮し、山守親分に大爆笑するとき祭は最高潮に達する。もちろんビデオで観ても十分に面白いのかも知れないが、それが劇場で観る『仁義なき戦い』の醍醐味は筆舌に尽くし難い高揚感があった。
ある意味、観客の質も変わったのだろう。ビデオで映画をパーソナルに観るのが習慣になってしまったのか、今回のオールナイトではオープニングとエンディングで拍手は起きても、客席が一体感になることに戸惑っていた雰囲気もあった。渋谷という土地柄もあったのだろうが、客層を見ると自分より若い連中が大半だった。
彼らにとっては、あくまで「30年前の名作」で、おそらく最初に観たのはビデオかテレビだったのではないかと思う。(昔、観ていたときは自分が一番若かったに違いない)
もちろん、私にとって『仁義なき戦い』シリーズは、もはや“絶対映画”の域に達しているので、新たな発見はあっても、今更どのような環境でもブレることは一切無い。それでも10年以上ぶりの再会ではある。それなりに年齢を重ねてきたことも踏まえて、残りスペースで五部作について書いていこうかと思う。
━━ 記念すべき第一部は終戦直後の焼け跡の呉から始まる。
改めてオープニングの小池朝雄のナレーション後、女の悲鳴から始まり広能が刑務所に送られるまでの闇市の場面の叩きつけたような映像は凄い。
まったくもって色褪せていないどころか、30年たってもこれを超えるテンションとスピードを擁す映画にはお目にかれていない。
この冒頭シーンは広能ひとりが突っ走っているようだが、山守以外のほぼ主要人物を一気に紹介しているという凄まじさで、一昨年、阪本順治が『新・仁義なき戦い。』のオープニングで、光化学スモッグが出て早期下校の閑散かつ牧歌的な校庭を映し出して意表をついたのは、いきなり深作欣二のようには出来ませんと宣言したようなものではないだろうか。
ただ前々から思っていたのだが、この第一作ではいわゆる“深作タッチ”こそ完成しているものの、“仁義なき戦い”タッチはまだ完成途上だった。これは笠原和夫の脚本にもいえるのだが、上田が射殺される床屋の場面、新開が駅員に化けた坂井組に刺殺されるホームの場面は、おそらく『代理戦争』以降にはあり得ない発想で、むしろ『ゴッドファーザー』や『バラキ』といったマフィア映画の影響が見てとれるのと、坂井と広能が車の後部座席で会話を交わす場面もやや情緒的で、深作映画でいえば『博徒解散式』の頃の“金バッチ黒背広もの”の雰囲気を残している。
エンディングの葬儀のシーンにしても、もともと続編を作る前提ではなかったためかシリーズでも唯一“物語”としてまとめられてしまった感がある。もちろん、これらは『仁義なき戦い』という不朽の名作のいささかの減点対象にはなっていないのだが…。
2003.2.8(土)渋谷東映
仁義なき戦い・広島死闘篇
1973東映/脚本:笠原和夫/出演:菅原文太/北大路欣也/千葉真一/梶芽衣子/成田三樹夫/山城新伍/前田吟/室田日出男/小池朝雄/川谷拓三/八名信夫/金子信雄

━━ 第二部は朝鮮動乱の時期の広島まで遡る。
実は初めて観た頃、この第二作は一番しんどかった。シリーズ全体の流れからすると番外編的な色合いが強く、まして集団劇の面白さをとことん追求したシリーズにあって、北大路欣也と千葉真一の芝居が突出した、唯一の個人劇であるという異色さと、神経ギリギリのバイオレンスが観ていてどうにも痛かったからだ。
今では結果として『仁義なき戦い・広島死闘篇』は、深作映画の中でも『同・代理戦争』『仁義の墓場』と並ぶベストだと思っている。
笠原和夫という当時から巨匠級の脚本家と、まだまだ「鬼才」扱いの深作欣二のコンビにとって、第一作は手探り状態だった感もあり、第三作以降は見事に調和してゆくのだが、この第二作はズバリ“対決”していた色合いが濃い。その対決の色合いが高校生の私にはしんどく、40過ぎたおじさんの私にはたまらなく面白いのだ。
笠原は、特攻隊に志願するも終戦によって行きはぐれた山中に自身の思いを投影させて描いたのに対し、深作は、終戦によって古い価値観が崩壊した土壌の中から生まれた狂犬のような大友に共感を抱いたという。結果として笠原の情念に対し、深作の破壊が対立軸となって、凄まじいばかりの暴力映画が誕生した。
後から知ったのだが、北大路と千葉とは逆の配役だったらしい。大モメの結果、クランクイン直前に変更となったらしい。今ではお互いに『広島死闘篇』を自身の代表作だと公言している。“神が降りる”とは、まったくこういうことをいうのだろう。
2003.2.8(土)渋谷東映
仁義なき戦い・代理戦争
1973東映/脚本:笠原和夫/出演:菅原文太/小林旭/梅宮辰夫/渡瀬恒彦/成田三樹夫/山城新伍/加藤武/田中邦衛/池玲子/川谷拓三/室田日出男/金子信雄

━━ 第三部から、いよいよ“広島戦争”に突入する。
笠原は延々91日間も擁して書き上げた脚本を深作に見せて言った、「一体これで映画になるのか?」。深作は断言した、「なる。」…かくして日本映画未曾有の群像ドラマが誕生する。
映画の核は“対決前夜”。とにかく多数の登場人物たちが、それぞれの思惑で複雑に絡み合い、精緻なプロットのもと映画はエンディングまで一気に加速していくという奇跡のような作品となった。もし、このシリーズが広島戦争から開始していたとすれば、ここまでの完成はあり得なかったに違いない。前二作品の蓄積がこの奇跡を可能にした。
主役も脇役もなく、殆ど全員が主要人物であり、無駄がなく、一切の隙もない。盃外交に明け暮れる親分たちと、それに翻弄される若者たち。あまりに人間関係が込み入っていて初めて観たときはすべてを把握することが出来なかったほどだ。
にも関わらず面白い。ともすれば人物の羅列に陥ってしまう危険性もあった。笠原が構築した人間模様を役者たちが熱演で応え、深作欣二がダイナミックに捌ききった。細部が理解できなくとも、全体を鷲掴みで観れば十分に楽しめる。当然、繰り返し観てすべてを把握すると更に面白い。これほど何度観ても飽きがこない映画も珍しい。
個人的には、渡瀬恒彦と池玲子が暗いアパートで結ばれる場面が好きでたまらない。青春が突っ走る一瞬の煌めき、身勝手な欲望と焦燥、そしてゆくゆくは破滅に突き進むであろう運命を「ドドンパ」のメロディが暗示する。傑作だ。
2003.2.9(日)渋谷東映
仁義なき戦い・頂上作戦
1974東映/脚本:笠原和夫/出演:菅原文太/小林旭/松方弘樹/梅宮辰夫/田中邦衛/夏八木勲/黒沢年男/小倉一郎/小池朝雄/小林稔侍/室田日出男/金子信雄

━━ 第四部は、戦後の高度経済成長と抗争の終結、世代交代がテーマとなった。
力だけがモノをいう終戦の焼け跡から朝鮮動乱を経て、急激に復興していくの渦の中に、男たちの欲望と流血を巻き込んで描いてきたこのシリーズは、やくざ映画に仮託された日本の戦後裏面史でもある。
前作で対立軸が明確となった広島戦争は、本格的な抗争から終結へと向かっていくのだが、深作と笠原コンビの目線は、この第四作を俯瞰で捉えているような気がする。
混乱から秩序を取り戻した市民生活に埋没し、次々と主要人物たちがリタイアしていく。抗争の展開としてではなく、あくまでも戦後史の力学の中に『仁義なき戦い』を完結させていくのだという強い意志だ。そこにひとつの時代の終焉と世代交代のドラマが絡んでくる。
懲役雪駄も寒々しく、拘置所で言葉を交わす広能と武田。数々の名場面に彩られたこのシリーズにあっても、『頂上作戦』のラストはシリーズの白眉とも言うべき屈指の名場面だろう。
2003.2.9(日)渋谷東映
仁義なき戦い・完結篇
1974東映/脚本:高田宏治/出演:菅原文太/北大路欣也/小林旭/松方弘樹/宍戸錠/伊吹吾郎/山城新伍/田中邦衛/野川由美子/桜木健一/中原早苗/金子信雄

━━ 第五部は、戦後処理と、経済やくざの台頭。そして流血の継続へ。
この『完結篇』は私にとって永遠の★3つ半作品だ。何度観てもシリーズは『頂上作戦』で完結している。
笠原和夫はこの先のエピソードは、相当ヤバイ話しに斬り込まざるを得ないが、しかし妥協もしたくないので会社に迷惑がかかるとして辞退した。
しかし、笠原和夫が手を引いたシリーズを高田宏治はよく引き継いだといえる。満塁ホームランでランナーが一掃した後にバッターボックスに立って、三遊間を抜けるシングルヒットを放ったという感じではある。
笠原自身が「高田君には自分が貯めていた資料をすべて渡したが、苦労をかけた。」と述懐している。残念だったのは、北大路欣也の再登板と、千葉真一が出られなかったことだろう。結局、生き残り組だった田中邦衛と山城新伍の凄絶な死がこの作品のエポックとなった。
その笠原和夫も深作が亡くなられる一ヶ月前に逝去してしまった。
以上、急ぎ足で五部作を一気に書いてきた。深作欣二という稀代の映画監督が『仁義なき戦い』という、世界でも類を見ない映像世界を展開させたことに限りないオマージュを捧げ、私はこの映画とめぐり合えた幸福を胸に、おそらく一生リスペクトし続けていくことだろう。
2003.4.30(水)三百人劇場
君が若者なら
1970松竹/脚本:中島丈博/松本孝二/深作欣二/出演:前田吟/石立鉄男/寺田路恵/河原崎長一郎/峰岸隆之介/荒木道子/大地喜和子/小川真由美/室田日出男

そろそろ浪人生活も板に付きはじめ(?)またしばらく深作欣二に没頭する予定。三百人劇場で「追悼特集 映画監督・深作欣二」と題し、深作作品全60作中、55本が一挙に上映される。“深作狂”を自認しつつも、初期作品まで観ているわけではないので絶好の機会ではある。
さて、この『君が若者なら』だが、おそらくあらゆる意味で最も知られていない深作作品だろうか。かつて、情報誌の上映一覧を参照して深作欣二を追いかけていたときも、この作品が上映されていたという記憶がない。70年代の作品なのでプリントがなくなっていたわけではないだろうが、私自身もこのタイトルを深作のフィルモグラフィで見ていたものの、殆ど気にも止めていなかった。とにかく、ここまで予備知識が皆無だった深作作品を観るのは初めて。今はクリックひとつでインターネットが内容を検索してくれるが、どうせ知らないのならば、まったく無防備で観てやれと思った。
九州の炭坑町で不遇の少年時代を送り、集団就職で上京した喜久男と麻男は、中卒のままでは一生浮かばれないと、3人の仲間たちと協力してダンプを購入し独立することを誓い合う。しかし、仲間のうち一郎は結婚して子供が生まれ脱落。竜次はピケ破りで警察に頭を割られて死亡。清は倉庫荒らしで刑務所へ送られてしまう。それでも喜久男と麻男は頑張り抜いて“独立1号”と名付けたダンプを購入。しかし刑務所を脱走し殺人犯となった清がふたりの前に現れたことで、事態は狂い始めてくる…。
タイトルから、これが青春映画であることはわかったが、深作的不良感度濃厚の作品なのかどうかはわからなかった。製作は1970年。この時期はアメリカンニューシネマ、日活ニューアクションに代表される反権力青春自滅映画が主流だったためか、やはり大らかなTV青春ドラマというわけにはいかない。
しかし、新星映画社=文学座=松竹の提携作品ということで、多少の左翼的ニュアンスはあっても決して不良性感度濃厚の青春ものではなかった。これが東映映画なら彼らは一旗揚げるため愚連隊化して大暴れとなるのだろうが、あくまでも今井正、山本薩夫の系譜的な正しいプロレタリアートを目指していく。
とにかく驚いたのが、手持ちカメラとフラッシュバックによる叩きつけるような深作タッチで全編が貫かれていたことだ。私はこのタッチの確立は『軍旗はためく下に』からだったと思っていたので、あまりの無知を恥じたい気になった。ただ本日続いて鑑賞した『恐喝こそ我が人生』もそうだが、深作の特長としてストーリー展開のスピードが先走るあまり、人物設定が次々と回想シーンのフラッシュバックで処理され、主人公の独白が延々と繰り返されることがあり、この作品は少々説明的すぎたきらいがある。
『広島死闘篇』の前田吟のキャスティングは不思議だったのだが、深作映画で主演を張った過去があったのだ。おそらく私が知っている前田吟のうち最も硬質で骨太だった。この主人公が刑務所を出所した後に広能の盃を貰ったとしても違和感がないほどに。
2003.4.30(水)三百人劇場
恐喝こそわが人生
1968松竹/脚本:神波史男/松田寛夫/長田紀男/出演:松方弘樹/佐藤友美/室田日出男/ジョー中山/諸角啓二郎/江原真二郎/川津祐介/天知茂/丹波哲郎

久々にカラーが退色して画面が赤くなり、絵とび、音とびの激しいプリント状態での上映にお目にかかった。よく『昭和残侠伝』の初期作品などで体験したのだが、1968年製作程度では、まだ大丈夫なはずなのに、と一瞬思ってしまった。笑ってしまう、今は2003年だった。プリントが痛んでいるのも当然か?さっき観た『君が若者なら』はおそらくロッテルダム国際映画祭で回顧上映されたときのニュープリントだったのだろう、33年前の映画とは思えないほどに綺麗だった。ただ英語字幕が邪魔で閉口したが…。
深作作品を55本集めた三百人劇場はよくやったと思うが、各回入れ替え制で、そのつど入場料をとるシステムは電車賃も含め、失業者には正直つらい。重複を避けながら作品を計画的に選別できるという利点はあるのだが…。
さて、『恐喝こそわが人生』。これも深作作品としては未見のうちの1本だ。ただ『君が若者なら』と違い、この映画は『ジャコ萬と鉄』同様、観るつもりで何故かタイミングが合わないままここまで来てしまった。絶対に観るつもりで観ていない映画は数多い。そうなってくると絶対にビデオ鑑賞なんぞでお茶を濁すのだけは止めようなどと思ってしまう。そのツケが結局は今日のような「追悼特集」での初鑑賞などという悲しいことになってしまう。
新宿で働いていたチンピラ村木は、昔なじみの仲間とつるんで恐喝を専門とする四つ葉会を結成する。村木たちは自分たちで作り上げたルールのもと、獲物を探し出しては次から次へと大金をせしめていくのだが、あるきっかけで政界の影の大立て者に狙いを定めたとき、仲間は殺され、村木自身も巨悪の罠に追いつめられてゆく…。
テイストとしては同じ松方弘樹主演で中島貞夫が監督した『893愚連隊』に近いが、組織として成り上がろうというよりもダチとの連帯を志向していく部分では『狼と豚と人間』で北大路欣也が演じた若者像に近い。これも松竹映画だが、『君が若者なら』と違い脚本の三人を含めキャスト的にも東映色が強い。おそらく暴力とエロしか客が入らなくなっていた当時の日本映画界にあって、松竹ではそれが撮れる監督がいなかったため、専属から契約となった深作を持ってきたのだろう。大船ではなく、どこまでも大泉撮影所の臭いがする作品だ。
驚いたことにこれもまた深作タッチで全編が貫かれていた。そもそも人物の過去をスチルやモノローグを使ってフラッシュバックで見せる手法は深作映画の常道で、最近になってビデオで再見した『火宅の人』『魔界転生』といった80年代の作品でさえ同じことをやっていた。
ただ、今日の2本はそれをやり過ぎていた感がある。とにかく展開を先へ先へと進めていこうとする深作のスピッリットが妙にやんちゃに思える。『人斬り与太』は別格として、若いチンピラたちを主役に添えた唯一の映画ということらしい。それにしても深作は「東京流れ者」のメロディがよほどお気に入りと思われるが、これが最初なのか。この先、三百人劇場でおいおい確認していこうかと思う。
2003.5.4(日)三百人劇場
新・仁義なき戦い
1974東映/脚本:荒井美三雄/神波史男/出演:菅原文太/若山富三郎/松方弘樹/渡瀬恒彦/宍戸錠/安藤昇/田中邦衛/池玲子/松尾和子/中谷一郎/金子信雄

25年前の映画鑑賞記録を見直してみた。この『新・仁義なき戦い』は“1978年6月18日新宿昭和館にて”とある。この作品に関しては、この日が初見だと思うが、この日より一ヶ月前に『宇宙からのメッセージ』の封切りを観ており、一ヶ月後に今はなき日本一の巨大劇場、銀座のテアトル東京にて『スター・ウォーズ』の第一作目をシネラマの大画面で観ている。映画が大きく変貌しようとする頃だった。更に驚くなかれ、前日にはリバイバル・ロードショーでイングマール・ベルイマンの『沈黙』を観ているのだから笑ってしまう。高校生の私は、とにかく映画に貪欲な熱情をほとばしらせていたようだ。
さてこの17歳の時に観た『新・仁義なき戦い』の鑑賞記録を読み返していると、これがまた笑える。
抜粋してみる。[〜さて、この作品の感想を書く前に自分の早合点を告白してしまおう、僕はこの8作からなるシリーズは全部続きものだと思っていた。だから4作目の『頂上作戦』の次は、これだとてっきり思っていたら、次の『完結篇』で広能昌三の話しは5作で終わりらしい。そしてこの『新・仁義なき戦い』で第2次抗争というのが始まるわけだ…] とトンチンカンなことが書かれていた。“完結篇”と銘打たれた以上は一番最後の作品だと思いこんでいたばかりではなく、新シリーズ3本が続きものだというトンチンカンの上塗りまでしている。もっともこの作品のエンディングで「この後、彼は日本全土を震撼させた抗争事件の台風の目となっていったのである」なんてナレーションが入れば普通はそう思っても仕方がない。
新シリーズがそれぞれ独立した単発の3本だったことは、一週間後に新橋第三劇場で『組長の首』を観て知ることとなる。いまや『仁義なき戦い』や深作欣二関連の出版物が相次いで刊行され、ビデオ店にはソフトが並び、インターネットで作品の検索も簡単になった。当時の私の知識は実際に映画館に足を運ぶことによって蓄積せざるを得なかったのである。
さらに当時の鑑賞文の締めくくりは [〜自分の手下たちが血を流しているときに、芸者と野球拳をのうのうとやっているところなど、相変わらずの山守ペースだった]と記されている。
この拙文で、シリーズの順番もわかっていなかった私が、山守というキャラクターに対して憤怒ではなく、おかしみを持って親しんでいた点が面白い。すでに『仁義なき戦い』を四部まで観て映画館の反応に感化され、観客(共犯者)たちとの“祭”を共有していたことがうかがえる。おそらくビデオでの鑑賞であれば、こういった感想にはならなかったに違いない。
それだけにビデオで「仁義」ファンになった連中が、関連オタク本を出版していることに疑問を持ってしまう。最初に“祭”を共有していない人に、シリーズの本質が理解できているとは思えないからだ。
“祭”といえば、深作自身がこの作品を正月映画らしいお祭り気分で仕上げたと供述している。シリーズ化の予定がなかった『仁義なき戦い』が四部作となり、あまりのヒットに『完結篇』が急遽作られ、今度は「新」をやれという東映商法の中で、この作品は第一部から、たったの2年で同じ監督・主演コンビでリメイクしてしまったというとんでもない企画となった。それを強いられた側は、「よしゃ、祭で乗り切ったれ!」と考えたのは十分に理解できるのだ。
そのためかどうかはわからないが、『新・仁義なき戦い』は前シリーズにあった緻密なストーリーや崇高な理念よりも、徹底的に下品な笑いが随所に散りばめられ、「客が笑って盛り上がってくれればいい」という居直りが全編に漂っている。
当然のことながら、ビデオ鑑賞者には不評を買っているようだが、当時の深作と文太の勢いなのか“祭”はしっかりと完成している。何度観ても面白いのだから…。
2003.5.4(日)三百人劇場
県警対組織暴力
1975東映/脚本:笠原和夫/出演:菅原文太/松方弘樹/梅宮辰夫/成田三樹夫/佐野浅夫/室田日出男/山城新伍/田中邦衛/川谷拓三/金子信雄/中原早苗/汐路章
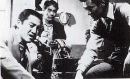
その柳の下にドジョウを何匹も生産し続ける東映商法に、深作ほど付き合いが良くなかったのが笠原和夫であり、『県警対組織暴力』はそんな笠原のストーリーテリングの巧さで一気に見せる傑作となった。
この作品は1978年7月31日に新宿昭和館での初見となっている。この時の感想文の書き出しが…[面白かった!さすが深作欣二である。そして、さすが笠原和夫である!〜] と興奮気味に始まっている。すでに『やくざの墓場・くちなしの花』は観ているので、高校生の目にも深作のみならず、脚本の笠原の存在も大きなものとして映っていたようだ。
奇しくも昨日、NHK教育テレビが「仁義なき戦いを作った男たち」というタイトルで、相次いで鬼籍に入った深作、笠原の足跡を検証するドキュメンタリーを放映していた。
岡田茂・元東映社長は笠原に対し「とにかく実証主義者。取材に出掛けて自分で納得するまで資料を作っていた。本を写すなんてことはしていなかった」と語っている通り、笠原が一本のシナリオに取り組むまでに如何に身を削ってきたことなどが、夫人の証言や自宅に保管されている膨大な資料とともに紹介されていた。
そもそも『仁義なき戦い』自体、主人公のモデルとなった美能幸三に映画化の許可を取り付けたのが笠原であり、シリーズ全体に散りばめられた豊穣なエピソードのひとつひとつが彼の流した汗とすり減らした靴底の結晶だったのだ。
笠原は昭和2年生まれということなので、私の父と同年ということになる。終戦は海兵基地で迎えたという。特攻隊に行きはぐれたという思いは、「わしのゼロ戦じゃ!」とばかり拳銃を振り回していた『広島死闘篇』の山中正治もそうだったが、とくに終戦の混乱は笠原に裏街道を歩く日陰者たちへの共感という形で影を落としていく。
『県警対組織暴力』は刑事とやくざを「集団就職の売れ残り」として同一線上に捉えることにより、日陰者たちの歌を可笑しさと哀しさのハーモニーで高らかに謳いあげた作品だ。
舞台となるのは昭和30年代の倉島市という架空の都市。しかし架空とはいいながらも、絵空事の雰囲気は微塵にもない。『仁義なき戦い』で蓄積した広島弁の見事さもあるが、地元やくざと刑事たちの腐れきった関係に人間の原罪のようなものが垣間見えるからだ。
例によって、ここにも随所に“笑い”が散りばめられている。ある意味、久能警部の殉職も滑稽だ。しかし依然として“人間喜劇”である以上、“笑い”は不可欠だ。「最後は笠原和夫二等兵曹として死ぬ」といっていた笠原の真骨頂がここにある。
2003.5.4(日)三百人劇場
解散式
1967東映/脚本:松本功/山本英明/出演:鶴田浩二/丹波哲郎/渡辺美佐子/渡辺文雄/待田京介/曽根晴美/小松方正/室田日出男/宮園純子/内田朝雄/河津清三郎

『解散式』はつくづく不思議な映画だ。内容も十分に不思議だが、この映画の存在意義が不思議でならない。
この作品は深作のフィルモグラフィにあって、常に『人斬り与太』『仁義なき戦い』との比較対照として取り上げられてきた。例えば “深作もかつては会社の路線に従って『解散式』のような映画を撮らされていた” とか、“『解散式』などを撮っていて、深作の胸の内に押さえきれない鬱屈が生じていた”といった具合で、このタイトルは不遇時代の象徴として、「深作欣二全史」に於いてのみ燦然と輝く存在となっているのだ。
内容そのものは、8年の刑期を終えて出所した鶴田浩二扮するやくざが、石油コンビナートの利権をめぐる組の争いに巻き込まれ、ついに堪忍袋の緒を切って敵地に殴り込むという、ありきたりのもので、任侠映画の構図から一歩も出ないものであり、この頃の東京撮影所で製作されていた鶴田の現代任侠ものは大概がこのパターンで話が進んでいく。
この時すでに深作は『誇り高き挑戦』『狼と豚と人間』が、一部の評論家に絶賛されるなど、その作家性には注目されていた。しかし客はまったく入らず、儲からない監督のレッテルを貼られていたこともあって、会社から任侠映画を撮らされた事情はよくわかるのだが、画一的な任侠美に対抗する意味で、もっとモダンで都会的な作品に仕上げなかったのだろうかという恨みが残る。
この映画で深作は、暴力団が市民社会に入り込み、経済やくざ化している設定の中で鶴田を全編に渡って着流し姿にさせた。冒頭から着流し鶴田の目線で首都高速道路を映し出し、近代的なビルへと移動していく。そしてすっかり有名になった石油コンビナートを背景に丹波哲郎との着流しやくざ同士の斬り合いの場面となる。斬り合いながらも古い価値観を共有する者同士のシンパシーが両者の間に漂うのだが、いうまでもなく大ヒットした『傷だらけの人生』にあるように、“古い奴でござんす”というイメージは鶴田がもっとも得意とする任侠ヒーローの美徳だ。その古風な任侠像をことさらに強調してしまうと違和感というよりも異常な滑稽感が生まれる。 本来なら「義理人情を抜いたら俺たちやくざに何が残る。」という台詞は、任侠映画としては“泣かせ”の道具として使われるが、石油コンビナートや愚連隊が闊歩するスラムがバックではどう見てもケレンを通り越しギャグにしか思えないのだ。
深作は作家性の強い監督だが、この段階で会社のドル箱を笑いのタネにしてまで任侠美を否定していくほどの突出した作家性があったとは思えない。意外とマジで鶴田の古さの美学を追究していたような気がする。『解散式』というタイトルも、冒頭で描かれる警察立ち会いの下で報道陣相手に親分が解散文を読み上げるものではなく、鶴田と丹波が組半天を燃やす儀式に主眼を置いていたともとれなくもない。
『解散式』は次作の『博徒解散式』同様、深作の仁侠映画が、山下耕作の実録もの以下であることを露呈した意味では、やはり深作映画としてのみ存在価値のある珍品だろう。
2003.5.4(日)三百人劇場
日本暴力団・組長
1969東映/脚本:神波史男/長田紀生/深作欣二/出演:鶴田浩二/若山富三郎/菅原文太/安藤昇/内田良平/中原早苗/一色美奈/水島道太郎/室田日出男/小林稔侍

未見の深作映画に出会える歓びは歓びとしても、やはり一日4本はきつい。もう若くはないことをこういう時に感じる。昔はオールナイトで5本立てを観た翌日に昭和館で3本観るなんてなんてこともやったし、他にももっと無茶苦茶な映画の見方をしていた。そもそも[24時間フィルムマラソン]を一睡もしないで完走したこともある。
もっとも若さ云々は別としても、一日2本までが正しい映画の見方の限界だろう。本当に気合いを込めてその映画と対峙しようと思ったら一日1本がいいに決まっている。今回の上映会は観る映画すべてに気合いを込めているだけに辛い。
ただ3本立て以上になると、昼下がりの眩しい太陽を浴びていた繁華街が、映画館を出る頃にはすっかり夜の顔に変貌しているという、あのトリップ感覚を思い出して懐かしかった。「こんな晴れた日に、暗闇の中で一日過ごしてしまった」と自嘲気味に面白がってしまう感覚は映画狂にしかわからない愉悦かも知れない。
その点、入れ替え制は必ず上映後に外へ出されるので現実感が伴い面白くない。それに4本観ても、5本分の時間がかかってしまうのももったいない話しだ。時間がもったいないのではない、貴重なフィルムの上映機会損失がもったいないのだ。
今回、この三百人劇場での「深作欣二追悼特集」にはチクチク文句を垂れてきたが、『県警対組織暴力』『解散式』『日本暴力団・組長』がニュープリントで観られたことは嬉しかった。残念ながら『新・仁義なき戦い』は色落ちが激しく、所々飛んでしまっていた。色褪せて赤褐色に変貌した画面は観ていて辛い。なにしろフィルムが死にかけているのだから。
その綺麗な画面に大写しとなる鶴田浩二の顔は本当に美しいと思った。この『日本暴力団・組長』は、若山富三郎、安藤昇、内田良平、河津清三郎といった凄みのある顔がズラリと鶴田の周りを囲むだけに、その端正な顔立ちが一層目立っていたように思う。
それにしてもこの作品の冒頭シーンには驚いた。スチールとニュース映像で戦後の闇市から高度成長までを見せ、ナレーションで「終戦直後の力がものをいう時代から、世界情勢が冷戦体制に変化するにつれ、やくざ社会も強大な組織が仕掛ける代理戦争の時代となった。」という説明から始まったのだ。
関西の巨大組織の関東進出に伴い、関西と手を結んだ横浜の組を、大同団結した関東の組織が潰しにかかるという大筋は、盃外交も伴って現実感のある設定で、『解散式』の時よりも集団抗争劇としての現代やくざ映画のスタイルは確立していた。
もっとも、ここで問題となってくるのが鶴田浩二のスターとしての佇まいだ。深作は鶴田浩二で7本撮っているが、あのイメージを最後まで崩すことはどうしても出来なかったという。
そのスターとしての資質があまりにも際立ちすぎていたため、本来、群像劇となるべきところが、どうしても鶴田を中心とした因果応報劇になってしまい、オープニングが大仰だっただけに、物語そのものが次第に失速していくのを感じてしまった。
しかし、『仁義なき戦い』の3年前の作品。すでに助走は始まっていたのだ。
2003.5.9(金)三百人劇場
ギャング同盟
1963東映/脚本:秋元隆太/佐治乾/深作欣二/出演:内田良平/三田佳子/佐藤慶/戸浦六宏/平幹二郎/アイ・ジョージ/曽根晴美/山本麟一/楠郁子/薄田研二

根来衆を大量虐殺した『柳生一族の陰謀』や人類の殆どを死滅させた『復活の日』を例外とすれば、『バトル・ロワイアル』が深作作品中最大の大量殺戮映画だと思っていたが、もしかするとこの『ギャング同盟』が殺し、殺される人数としては上を行くかも知れない。とにかくモノクロの画面一杯に撃ち合いが展開されるという、命が空気よりも軽く扱われている映画だった。
といっても凄惨な殺しがグロテスクに展開する映画ではなく、どちらかといえば元気一杯に西部劇よろしくガン・アクションが炸裂するバイタリティ溢れる痛快作だ。
終戦から復興した東京。闇市で大暴れしていた風間は、娑婆に出ると昔の仲間を再結成し、縄張りを奪い膨張した組織の会長を誘拐。身代金として6千万を要求するのだが…。
東映のギャング映画は、東宝の岡本喜八の『暗黒街』シリーズとは若干違う色合いで、禁酒法時代の暗黒街を舞台にしたアメリカ映画のような黒ずくめの集団が、チャンバラ時代劇をピストルに持ちかえ、ひたすらドンパチに終始するイメージが強い。まだ現代やくざ映画が確立する以前の話しで、やがて暴力団という言葉が定着してくるにつれ、ギャング映画は“金バッチ黒背広もの”というジャンルへと変貌していく。その部分でいえば、『ギャング同盟』はギャングものの軽るさと、銃は無制限にブッ放すが、女は犯せないという甘さを残しながらも、むしろタイトルを『愚連隊同盟』とした方がしっくりくる設定になっており、今もし、この作品を再映画化するのであれば、絶対にギャング映画として認識されることはないだろう。
鶴田浩二といったビッグネームが出ていないので、おそらく添え物として作られている分だけ自由奔放にスピーディでスタイリッシュな仕上がりを見せ、最後まで飽きさせることはない。
『ギャング同盟』は出だしから『仁義なき戦い』そっくりに作られているように、終戦直後の青空幻想に思い入れ、戦後民主主義の虚妄性を描き続け“焼け跡回帰願望”がもろに描出されている点で、徹底的に深作映画たらしめている作品だ。
オリンピックを翌年に控えていた時代状況が、工事中の首都高速3号線の風景などにも映し出されており、そんな風景の中で彼らが苛立っているのは、闇市時代のアナーキーな風土で好き勝手に暴れてきた自分が、民主主義の中で去勢されつつあることへの焦りである。
今日も新宿西口では教育勅語の復興を標榜する集団がビラを撒いてアジっていたが、戦前と戦後の価値観の対立という図式は、思想にしろ、政治にしろ、社会風土にしろ、未だに議論されているテーマではある。しかし“終戦直後の焼け跡闇市時代”という一時期は、この平成の世にあって随分と語られなくなってきたような気がする。焼け跡に立って軸足を戦前にとるか戦後にとるかという基準としての役割しかなくなってきているのではないか。焼け跡の先には、もう戦後だけが控えているのだから、深作欣二、笠原和夫の死はある意味で映画に於ける“焼け跡闇市派”の死ともいえるかも知れない。
三田佳子のヒロインがやや観念的だった嫌いはあるものの、最後に激闘の残骸の中で生き残ったふたりを見下ろすのが綺麗な青空だったりするのもいかにも深作らしい。
2003.5.11(日)三百人劇場
狼と豚と人間
1964東映/脚本:佐藤純彌/深作欣二/出演:高倉健/三國連太郎/北大路欣也/中原早苗/江原真二郎/石橋蓮司/岡崎二朗/泗水誠一/沢彰謙/室田日出男

類い稀なるバイオレンス映画であり、人間ドラマであり、青春映画である。この作品を初めて観た大学生の時、深作欣二の映画を常に『仁義なき戦い』を中心に見ていた自分は鈍器で殴られたような衝撃を感じた。高倉健の“狼”、北大路欣也の“人間”、三國連太郎の“豚”という三者三様の図式の中で、やはり北大路と、それを取り巻く仲間達のギラギラするような青春の栄光と挫折が、隙間だらけのスラムの倉庫からこぼれる落ちる熱い太陽の下に照射されるようで、20歳そこそこだった私にとっては絶対的な輝きを放つ青春映画だった。
あれから二十数余年。未来よりも過去の領域が自分の中で広がるにつれ、この文章をすべて過去形によって記しているように、作品の印象も微妙に変わってきた。
まず『狼と豚と人間』というタイトルに合わせて三者三様の図式などと単純に当てはめてしまっていいのかという疑問。三國連太郎的な生き方を“豚”として簡単に切り捨て、自分を含め大抵の日本人にそれを批判する資格があるのかという疑問。同時に北大路欣也のグループに一方的に正義を見いだし青春映画の傑作などと決めつけてしまったことへの疑問。今日、改めて観てこの3つの疑問が噴出するのが禁じ得なかった。
スラム街で育った三兄弟は生き方や考え方がそれぞれ違い、互いに敵視し合っている。一郎は老母の金を奪ってヤクザの幹部になっている。次郎は金を信じて人間を信じない一匹狼でヒモ稼業。三郎は、同じ年頃の仲間とつるんで鬱屈した毎日を送っていた。ある日、次郎は一郎が所属する組織の麻薬資金を強奪する計画を三郎に持ちかけるのだが…。
今回驚いたのが、三郎を中心とした若者たちの連帯が崩壊していたこと。初見の時は、彼らの若さがもっと画面一杯にほとばしっていたように感じていた。『ウエストサイド物語』を彷彿とさせる舞台劇調の演出の印象が強かったためだ。確かにこの映画では彼らこそがまっとうな“人間”として描かれているようでいて、実は“狼”にも“豚”にも転ぶ危うさを内向していることに気がついた。極端な言い方をすれば“豚”として描かれた一郎こそが、“狼”としての牙を隠し持っており、それこそが“人間”の本質なのではないかとさえ思ってしまったのだ。
「いっぺん何もかもぶっ壊して、俺たちの組をブッ立てる」という三郎たちの夢想は、高度管理社会の象徴ともいうべき一郎はもちろん、この状況からの逃亡を目論む次郎とも違う価値観の中で足掻き苦しむことになる。これは明らかに繰り返し追い続けてきた深作テーゼだ。
それにしても広能組が仕切る「原爆スラム」に至るまで、深作が延々と描き続けてきたスラムの風景が、この映画では突出している。ある意味、被差別部落問題をアクションに仮託して挑んだ告発映画なのかも知れない。しかし誰もがこの作品に傾向映画的感触を抱くことはないのは、それ以上に深作独特のスピード感とバイオレンスの噴出を見い出してしまうからだろう。
本日、上映後に深作夫人である中原早苗の対談が催され、実は初めて『狼と豚と人間』を観たのだという。「ヌーベルバーグのようでびっくりした」という感想が微笑ましかった。
脚本は深作と佐藤純彌のオリジナル。実によく書けたシナリオだと思う。
2003.5.14(水)三百人劇場
やくざの墓場・くちなしの花
1976東映/脚本:笠原和夫/出演:渡哲也/梅宮辰夫/梶芽衣子/佐藤慶/金子信雄/大島渚/藤岡琢也/室田日出男/藤岡重慶/川谷拓三/小林稔侍/千葉治郎/今井健二
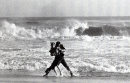
『人斬り与太』は2本しか作られなくても、シリーズと括られている記事はよく目にするが、この『やくざの墓場・くちなしの花』と、前年の『仁義の墓場』を称して、深作=渡による「墓場」シリーズと呼ばれることはあまりない。私も、仮に「墓場」シリーズなどと紹介している記事を目にすれば、もの凄い違和感とともに反撥を抱くのではないかと思う。
それにしても『仁義なき戦い』から『北陸代理戦争』に至るまでの実録路線と呼ばれる深作映画にあって、この渡哲也の2本は特別な存在であるように思えてしまうのは何故だろう。
集団群像劇ではないからとも言えるだろうが、私はこの2本が完全に渡哲也というスターによるスター・システムの映画であり、深作欣二の円熟した演出力がもたらした監督主義的な映画であるという二つの要素が見事に融合した結果ではないかと思っている。つまり黒澤作品に於ける『用心棒』と『椿三十郎』と同じ位置関係にあるのではないか。だから個人的な印象として、同じ笠原和夫の脚本で悪徳警官の破滅を描いた前年の『県警対組織暴力』とも違うものを感じてしまうのだ。深作ムーブメントである実録路線という激流にあって、渡の2本は流されることのない岩のように、水をかき分けてドカンと存在している印象だ。
もちろん、そのことを深作が十分に意識していたかどうかは不明だが、少なくとも笠原の方には、この映画は一連の路線のひとつという位置づけにするつもりはなかったに違いないし、『仁義の墓場』を絶賛しつつも、それに影響されることはなかった。
笠原がここで斬り込んでいったのが民族問題だった。やくざ社会の相当数は在日か同和で構成されているといわれており、俗に「“ち”の字と“ぶ”の字の映画はタブーや」という興行会社としての常識の中で、笠原が膨大な取材と、築き上げてきた実績の中でそのタブーに何度も阻まれ、妥協を強いられてきたことは想像に難くない。本当は『博奕打ち・総長賭博』や『仁義なき戦い』でも切り捨てざる得ない重要な要素として被差別部落問題は存在していたらしい。
日陰者には日陰からの実情とそれに伴う慟哭がある。不良性感度の部分だけでやくざ映画を捉えるのは偽善なのかも知れない。事実、笠原は昭和48年の「シナリオ」誌にしたためている。「『映画藝術』で帷子輝氏が御指摘のように、被差別階級と在日朝鮮人の抑圧の状況を抜きにして真実のやくざ映画は作れない。この問題については、作さんと近い内作品としてお応えするつもりなので、暫く時間を貸して頂きたい。」
その“応え”が『やくざの墓場・くちなしの花』であることに異論はない。しかし、笠原は「昭和の劇━映画脚本家 笠原和夫」という対談本の中で、梶芽衣子の日本人と朝鮮人のハーフが、渡哲也の黒岩刑事に向かって叫ぶ台詞「日本人は信用でけへん」を映画では「デカはヤクザより信用でけへん」に変えられていたことに関し、「全然、テーマが違うものになってきちゃう。しかし、監督というのは、よう裏切るわね(笑)」と語っている。
台詞を変更した深作の真意はわからない。深作映画のある種エスプリであるスラムの描写は、差別問題を匂わせてはいたが、どちらかといえばスラムに焼け跡闇市の幻想を仮託していた色合いが強い。もしかすると近日刊行予定という山根貞夫著「映画監督・深作欣二」で、深作が全60本すべてについて語っているというので、その部分が触れられているのかも知れない。しかし、テーマを深化すればするほど娯楽の王道としての東映やくざ映画仮託していた色合いが横に逸れていくという矛盾と、真実のやくざ映画を完成させようとすれば避けられないテーマであることの矛盾。このジレンマは、深作欣二と笠原和夫という稀代の作り手たちの間にも横たわっていたのだろう。観客としては笠原脚本のままでは“刺さりすぎる”とも思うだのが…。
案外、深作にとってはこの作品の撮影中に度重なった大阪府警からの内容変更の圧力に業を煮やして前述の台詞にしてしまったのかも知れない。
この映画の頃から中島貞夫の『実録外伝・大阪電撃作戦』や山下耕作の『日本暴力列島・京阪神殺しの軍団』などで在日が描かれ出すのだが、それでも朝鮮人の抑圧された問題をここまで照射したやくざ映画は『やくざの墓場・くちなしの花』以外にはないというのも事実だ。笠原は不満だったのかも知れないが、改めて観てもやはり傑作だった。
2003.5.14(水)三百人劇場
ギャング対Gメン
1962東映/脚本:佃島栄/出演:鶴田浩二/千葉真一/梅宮辰夫/丹波哲郎/佐久間良子/沢たまき/織本順吉/砂塚秀夫/加藤嘉/曽根晴美/富田仲次郎/神田隆

『ギャング対Gメン』は折角のセミ・オールスターキャストだったにも関わらず、82分と短く刈り込みすぎて会社から睨まれたが、三島由紀夫が賞賛したために沙汰止みとなったという逸話があるらしい。『博奕打ち・総長賭博』といい、三島は意表をつく形でやくざ映画に貢献している。確かにこの作品は深作初のカラー映画で、クライマックスでは倉庫を丸ごと燃やしてしまうなど、成る程それなりにバジェットがかかったものになっていた。
当時、朝日新聞が「残酷で見るに耐えない」と批判していたことからもわかるように、まだ日本映画が大らかな時代だった頃の産物とはいえ、これが残酷というのであれば『人斬り与太』などどうなってしまうのか。前にも触れたように東映のギャングシリーズは、着流し任侠ものの現代版ではなく、あくまでもチャンバラ時代劇に『アンタッチャブル』の味付けを施した荒唐無稽なファンタジーであるため、この作品もその辺りの大らかさが反映されており、観ていて苦笑してまうこともしばしばだった。
『県警対組織暴力』は岡田茂社長が小便をしながら思いついたタイトルで、笠原和夫をして「何てダサいタイトルだ」と嘆かせたというが、『ギャング対Gメン』というタイトルのセンスの大らかで可笑しいと思っていたら、クレジットに “製作・岡田茂” と出ていたので笑ってしまう。
警察から極秘にギャング組織の探索を依頼された元やくざが、7人の集団を結成して組織に戦いを挑むという話しなので、さすがに『誇り高き挑戦』を撮り終えた直後の深作とはいえ、そこに作家性を持ち込むことは臨むべくもなく、岡田茂の目も光っていたためか、次作の『ギャング同盟』と比べて、いつもの飛び跳ねるような深作映画の躍動感は皆無に近かった。
よって会社が激怒したという82分の上映時間はまったく気にならなかった。もちろんこれはホメ言葉ではない。余談めくが、集団劇を描くには7人という単位が観る側の心理にもっとも適切な人数らしい。『七人の侍』と同様に、この映画も生き残ったのは3人だった…。
2003.5.14(水)三百人劇場
ジャコ萬と鉄
1964東映/脚本:黒澤明/谷口千吉/出演:高倉健/丹波哲郎/山形勲/江原真二郎/高千穂ひづる/南田洋子/大坂志郎/入江若葉

個人的に苦節25年。ようやくこの映画を観ることが出来た。まだ『蒲田行進曲』も『火宅の人』もなかった時代に、深作欣二のプロフィールが紹介されるたびに『ジャコ萬と鉄』は一般的に代表作として挙げられていた。もちろん脚本に黒澤明とあるように、もともと谷口千吉監督作品のリメイクとして、タイトルに知名度があったからなのかも知れないが、数少ない高倉健主演の深作映画として、学生時代は常にこの映画は鑑賞希望リストに入っていた。
浅草や文芸坐あたりで、あるいは秋の学園祭の時期にどこかの左翼系サークルの上映会でもよくやっていたという記憶もあるのだが、何故が観る機会を逸しながらここまで来てしまった。何故かタイミングが合わずにすれ違ってしまう映画ってあるのだ。
北海道のニシン漁期、片目の無法者ジャコ萬が流れてきて、無法の限りをつくすが、弱みを握られている網元は手が出せない。そこへ網元の息子で、正義感の強い鉄が戻ってきた。
“男騒ぎする映画”とはこのことかと思った。北海の荒海、殴り合い、男たちの怒号、ニシンの大群と、モノクロシネマスコープの画面一杯に男が乱舞していた。深作が黒澤脚本をどこまで忠実に撮っていたのは知らないが、いかにも三船敏郎をキャスティングに想定した黒澤らしい豪快な男性映画に仕上がっている。
その意味では、闇市もスラムも戦後もない北海道の大海原を背景とした深作作品としては、ある意味で習作に近い感覚だったのかも知れないが、漁師たちが車座で画面を囲んでいる場面などの群衆の描き方は、深作の持つダイナミズムが息づいており、何よりもクライマックスへと転がしていくドラマツゥルギーはさすがだった。
主要3人の役者の熱演も光る。同じ昭和39年には『日本侠客伝』がスタートし、“高倉健=任侠の徒”というキャラクターが定着する以前の健サンが、やんちゃな暴れん坊の雰囲気を画面一杯に展開させ、早くも北海道といえば健サンというイメージの片鱗を見せつければ、さっきの『ギャング対Gメン』のようなクールな悪漢像をかなぐり捨てるように、ひげ面に黒の眼帯をつけたマタギ姿の丹波哲郎はこれでもかと傍若無人に男の体臭を表現している。
この男ふたりの対決劇に翻弄される形の山形勲は、ジャコ萬の執拗な憎悪に怯えながらも、ヤン衆たちには居丈高に振る舞い、倅の鉄の奔放さに手を焼きながらも嬉しくて仕方がないという親バカぶりを見事に演じ分けていて圧巻だった。
それだけに当時の「映画芸術」に出ていた批評のように「ヤン衆たちの差別問題、アイヌ問題とこの時代のニシン漁に内在していた様々な社会問題が娯楽映画の中に埋没している」という指摘は見当違いも甚だしい。とかく左翼系論者の深作評は的はずれとしかいいようがない独りよがりなものが多い。一体、大衆に受け入れられることこそ最大の使命であるはずの三角マークの雄・深作欣二に何を求めているのだろうか?
谷口千吉の『ジャコ萬と鉄』は観ていないので何ともいえないが、この深作版は『蟹工船』ではないのだ。
繰り返し言うが、これは北海の荒海に展開する男たちの熱い心意気をアクションの中に描いた豪快な男性映画であって、それ以上もそれ以下の意味もない。だから面白いのだ。
2003.5.20(火)三百人劇場
黒蜥蜴
1968松竹/脚本:成沢昌茂/深作欣二/出演:丸山明宏/木村功/松岡きっこ/河津祐介/三島由紀夫/宇佐見淳也/小林トシ子/小田草之助/佐藤京一/丹波哲郎

これは「怖いもの見たくなさ」ともいうべきか、『恐喝こそ我が人生』や『ジャコ萬と鉄』とは逆に、『黒蜥蜴』と『黒薔薇の館』の連作は、今まで観る機会がなかったわけではないが、観ないでおいた作品ということになる。
深作が仁侠映画のドラマツルギーに馴染めないまま悶々としていたということが、一般的に知らしめられたのは、『人斬り与太』の登場からだと思うが、その作品履歴を眺めていると、『北海の暴れ竜』を観た俊藤浩滋プロデューサーが、「あいつ(深作)に仁侠映画の撮り方を教えてやる」いって『解散式』と『博徒解散式』を撮らせて、その後に深作の東映退社という経緯があり、松竹で仁侠映画と対極にある江戸川乱歩の『黒蜥蜴』を選ぶという流れに、むしろ顕著に深作の任侠嫌いの一面が見えている。
もっとも90年代には、監督・深作欣二、主演・木村拓哉で『怪人二十面相』というのが、よく企画ラインアップ表に載っていたので、まんざら乱歩的耽美の世界は嫌いではなかったのかも知れないが…。
世界的宝石商の岩瀬は、娘早苗の誘拐と、時価一億円のダイヤ “エジプトの星”の強奪を予告する女盗賊・黒蜥蜴におびえ、探偵明智に警護を依頼した。黒蜥蜴は早苗を誘拐したものの、明智は機敏な処置で、早苗を奪い返したが、黒蜥蜴もさるもの、明智に追いつめられても慌てず、わずかな隙をみて逃走する。それから半月後、的場刑事率いる警察陣に守られた岩瀬邸から、早苗が忽然と姿を消した。明智が駆けつけた時は、早苗と引換えに“エジプトの星”を持参せよ、という置き手紙が残っているだけだった…。
正確には江戸川乱歩原作の映画化というよりは、三島由紀夫が丸山(美輪)明宏の舞台のために書き下ろした戯曲の映画化ということになる。この『黒蜥蜴』という舞台は現在でも再演され続けている美輪の当たり役であり、この35年前の映画でも美輪の独壇場という趣向で全編が貫かれている。
ところが、やくざ映画以外の作品には、非日常的な突出したキャラクターを深作は時折見せることがある。『柳生一族の陰謀』『宇宙からのメッセージ』の成田三樹夫、『魔界転生』の沢田研二、『里見八犬伝』の夏木マリ、『必殺4・怨みはらします』の真田広之、『忠臣蔵外伝・四谷怪談』の石橋蓮司や蟹江敬三にその姿を見ることが出来る。これを勝手に厚化粧の狂人カリスマ・キャラと名付けてしまうのだが、『黒蜥蜴』の美輪明宏はその典型であり、原点だ。
ただ残念ながら、前述のキャラは深作が作り込んだ分だけの自由があったが、三輪のイメージはあまりにも確立し過ぎてしまい、美輪の華々しくも毒々しいイメージを、木村功演じる明智小五郎を極端に地味に描くことでコントラストを際立たせるという表現にとどまり、乱歩調のデカダンでアブノーマルな耽美感を出し切れていたとは言い難かった。
それにしても三島由紀夫の肉人形ぶりにはうけてしまった。本当は三島自身が明智を演じる案もあったそうだ。その方が深作らしい“怪作”になっていたのではないか。
2003.5.20(火)三百人劇場
黒薔薇の館
1969松竹/脚本:松田寛夫/深作欣二/出演:丸山明宏/田村正和/小沢栄太郎/川津祐介/松岡きっこ/西村晃/内田良平/ジョー山中/室田日出男

突然現れた謎の女、藤尾竜子は“黒薔薇の館”という名の古い洋館の社交クラブで愛を歌い、男たちを陶酔させていた。しかし崇拝者たちの中には、誰一人として彼女の心を射る者はいない。その歌声は求め続けながらまだ獲得出来ない“絶対の愛”についての嘆きだった。そんな時、傷ついた若者が彼女の前に現れた。追いつめられた彼の姿は、彼女の心を強烈に惹きつけ、やがてふたりの死をも恐れぬ至上の愛が美しく燃えていく…。
横尾忠則によるサイケなタイトルバックが終わると、真っ赤な夕陽に照らされた現実感のない海辺の街。不具合な洋館と豪奢なクラブ。黒薔薇を抱いた女が歌うボレロ。全体に漂うデカダンなイメージと、レトリカルな台詞の数々やフランス語が出てくるなどの妙な西洋趣味。映画はオープニングからただならぬ雰囲気で、まるで「これは凄まじいものを見せられる」という覚悟を観客に強いているようだった。
映画は、“魔性の女”の前に男たちがうろたえ、狂っていく様が延々と映し出されていく。これは『黒蜥蜴』とは違い、松田寛夫と深作欣二が美輪明宏のイメージで書いたオリジナル脚本の映画ということだが、美輪がイメージである以上は演劇的な空間が描出される。
ところが、サイケでアングラな60年代末期のカルチャーを映し出し得ていたかというと、実はそうでもない。内容はともかく意外と構図そのものはまともな純愛映画だった。オープニングで覚悟を強いられた分だけ拍子抜けの感は否めなかったが、明らかな失敗作としても決してつまらない映画ではなかった。少なくとも『黒蜥蜴』よりも愛すべき点は多い。
80年代あたりからのオタク・ブームの延長線上で90年代には、この手の映画をネタに扱う薄っぺらなポップカルチャー気取りの出版物が相次いで刊行されたが、『黒蜥蜴』にしても、この『黒薔薇の館』にしても石井輝男や佐藤肇の諸作と同一線上に語られることがなかったのは不思議としても、『ツィゴイネルワイゼン』の頃の鈴木清順ならもっと凄い映画になっていたのではないかという恨みは残った。
思えば、男たちが次々と魔性の女に心を奪われ破滅していくという話しは、よく聞く物語ではあっても小説や民話や舞台の領域であって、映像で描写するのは難しい。かのエリザベス・テイラーでさえ『クレオパトラ』で失敗したように、当然、そこまでの女をどの女優がリアルに説得力を持って演じられるかどうかという問題がある。
篠田正浩が『夜叉が池』で坂東玉三郎を使ったように、やはり既成の女優には不可能で、男が演じた方が、いきなり“虚構”という前提が出来るだけに楽なのだろうか。その意味では美輪明宏は格好の素材だとなるが、案外、素材が決まりすぎたのが小さくまとまってしまった原因なのかも知れない。
また舞台とは違い、芝居がカットで分断され、カメラが寄ったり引いたりする映画では美輪明宏の本来持っているスケールが生かし切れていないようにも思えた。とにかく深作の“異形好き”が垣間見られた1本ではある。
2003.5.20(火)三百人劇場
新仁義なき戦い・組長の首
1975東映/脚本:佐治乾/田中陽造/高田宏治/出演:菅原文太/山崎努/梶芽衣子/成田三樹夫/ひし美ゆり子/渡瀬恒彦/室田日出男/三上寛/小林稔侍/西村晃

『組長の首』は誰が何と言おうと面白い。確かに笠原和夫の作劇術と比べれば、繊細ではないが大胆ではあるし、重みはなく、徹底的に軽いが、おそよ“仁義なき戦い”のタイトルがついたどの作品よりも最高の疾走感を味わうことが出来る。だから何度見ても面白い。現に今こうしてスクリーンで再会した直後でさえ、帰宅してビデオで観てもいいくらいだ。『広島死闘篇』は満点に値する作品だが今年はもう観たいとは思わない。その意味で『組長の首』は特筆すべき“軽み”の面白さに満ち溢れている。
何故、これほどまでに面白いのかというと、娯楽映画が必要とされる要素がふんだんに盛り込まれているからに他ならない。娯楽映画の王道とも言うべき不良性感度濃厚のやくざ映画であるという前提をもとに、バイオレンスはもちろん、アクションあり、サスペンスあり、権謀術数が渦巻く人間模様あり、青春映画のお涙あり、ひし美ゆりこのお色気ありと、まるで幾重にも積み重なったおせち料理のような物語を深作の独壇場であるスピード感で一気に94分を叩みかけていくのだ。特に凄いと思うのが、カー・バトルが少々サービス過剰だったことを除けば、ほとんどダレ場がなかったことだろう。
深作欣二という映画監督を語るときに、確かに終戦の焼け跡幻想や、戦後民主主義の虚妄を批判するという作家性は無視できない要素ではある。しかし、60本にも及ぶフィルモグラフィからあぶり出される感慨は無類の面白主義と活動屋としてのサービス精神の旺盛さではないだろうか。
まったく80年代から90年代のことを思うと夢のような話しだが、この1975年という年に深作映画は5作品も公開されている。当時のキネマ旬報には作りすぎだと批判されていた。しかし、作品を選ばせないまま量産させた東映をよくぞやってくれたと思っている。「映画作家」だといえないこともないが実体は「活動屋」であるという深作の二面性が『新仁義なき戦い』『仁義の墓場』『県警対組織暴力』『組長の首』『資金源強奪』という1975年ラインアップにそのまま反映されているからだ。
説明無用の情念の劇『仁義の墓場』や、笠原ドラマの真骨頂『県警対組織暴力』で作家性を存分に発揮して世間を刮目させた分だけ、『組長の首』は前シリーズのイメージからも開放され、批評のマナ板を無視できる潔さに徹することが出来たのだろう。
まず舞台を北九州に移したことで“仁義なき戦い=広島”という呪縛が消えたことが大きい。使われる方言が違うだけではなく、実録の縛りもなくなったことで、ある意味で人間群像の中でがんじがらめになってしまった文太のキャラクターを自由にしたことも大きいと思った。
この年の深作の旺盛な創作意欲は(多少、ヤケぱち気味の部分もあるが)実は、この五本の公開作品にとどまらず、『Gメン‘75』といった数本のテレビ作品にも及んでおり、重ねていうようだが、80年代の大作主義の渦中で失速気味だった深作を思うと、製作条件の善し悪しとは、一体何だろうと思ってしまう。量産体制には功罪が半ばするだろうが、この作品は功と出た量産体制の落とし子だといってもいい。
2003.5.26(月)三百人劇場
現代やくざ・人斬り与太
1972東映/脚本:石松愛弘/深作欣二/出演:菅原文太/渚まゆみ/安藤昇/室田日出男/待田京介/小林稔侍/小池朝雄/内田朝雄/地井武雄/谷本千夜子/諸角啓二郎/

この作品を、『仁義なき戦い』より好きだという深作フリークは意外と多い。安保闘争が終結し、反動で連合赤軍事件が勃発するという社会背景。映画もアメリカン・ニューシネマから『ゴッド・ファーザー』『バラキ』といったマフィアものが大ヒットしていった中で、とくに「仁侠映画=マンネリ化した大衆迎合」などと言っていた当時の映画青年たちにとって、カタギを脅し、女を犯し、痛みには悲鳴を上げる狂犬のような主人公の『人斬り与太』が突如と出現したときのインパクトは相当なものだったに違いない。
しかし悲しいかな“遅れてきた深作信者”にとって、この『現代やくざ・人斬り与太』は既にファーストインパクトではなかった。『仁義なき戦い』はもちろん、狂犬やくざものの極北ともいえる『仁義の墓場』の洗礼もすでに受けてしまっていた。だからこの作品についてはムチャクチャなバイタリティは感じ取っていたものの、ヒーローものの既成概念をぶち破られたという快感はなかった。むしろ追体験という映画の見方は時間軸にもリアルタイムな社会背景にも影響されない分、任侠も実録も一緒くたに受け入れてしまうために、『現代やくざ・人斬り与太』をその中に吸収させてしまった気がする。
ところがこの映画を観るのは今日で3回目の鑑賞となるが、なにせそのスパンは30年近くに及ぶ。初めて観たという感覚に陥ったのも仕方のないことで、その通り、実際、純粋にこの作品と対峙したのは今日が初めてだからだ。
ニュープリントによる綺麗な画面も嬉しかったが、それよりも何よりも、この作品の構成がここまで見事だったことに目から鱗が落ちる思いをした。
川崎を根城とする諸角啓二郎が親分の老舗と、安藤昇を親分とする新興の2つの組があり、その2つの組が狂犬やくざに翻弄されるというのが骨子なのだが、2人の親分を決してステレオタイプには描かず、安藤昇は狂犬にかつての愚連隊だった自分を投影して望郷の念に駆られ、何とかこの狂犬を生かしてやりたいという人物として設定し、劣勢だった諸角啓二郎の組も関西の巨大組織の関東進出に手を貸す代わりに、この地での形勢を逆転させようと画策させるといった具合に、文太の暴れっぷりだけで全編を突っ走ってしまった『狂犬三兄弟』と比べてもなかなか贅沢な脚本になっている。
確かに『現代やくざ・人斬り与太』は『狂犬三兄弟』から『仁義なき戦い』を経て『北陸代理戦争』まで至る深作実録路線への流れと比較すればメロウであり、“主人公が一番悪い奴で何が悪いのか?”という有名な深作のコメントはあるが、まだ若干、観客にヒーローとして肯定的させようとする甘さも残っている。
例えば、文太と渚まゆみの繋がりが肉体的な関係としてではなく、赤飯の握り飯に象徴される母親幻想だったりするあたりは徹底的に甘い。所見の時に今ひとつ乗り切れなかったのは、徹底的な暴力映画という定説にこだわってしまったあまり、日陰者同士のメロドラマという側面に面白さを見出せなかったことと、小池朝雄のインテリやくざがともすれば狂犬の疾走感を阻害しているように感じられたからだ。
しかし、最後に観てから23年。今日はこの映画の情緒的な部分がやけに胸に沁みていた。渚まゆみは『狂犬三兄弟』の薄幸のイメージが強烈だったあまり、このバイタリティ溢れるパン助役を若い頃は引いて観ていたのかも知れない。ある意味、文太のキャリアの中でもっとも手の合った女優だったのではないだろうか。
また深作は『蒲田行進曲』で松坂慶子をブレイクさせるまではずっと「女を描くのが下手」だというのが定説になっていたし、深作自身もそれを認めるような発言をしていたのだが、マキノ雅弘的な女性描写に価値観を持たなければ深作は決して女を撮るのが下手だとはいえない。この男根主義の権化のような2本で見せた渚まゆみは眩しいくらいに輝いていた。
それにしても『現代やくざ・人斬り与太』をまともに評価し、素晴らしい映画であると認知するのに、30年も費やすとは、かくも長き時間を要したものだ。
2003.5.26(月)三百人劇場
人斬り与太・狂犬三兄弟
1972東映/脚本:神波史男/松田寛夫/出演:菅原文太/渚まゆみ/田中邦衛/三谷昇/内田朝雄/渡辺文雄/室田日出男/小林稔侍/菅井きん/須賀不二男/三原葉子

『人斬り与太・狂犬三兄弟』の初見は、記録によると1980年の5月となっており、これは『仁義なき戦い』の初見より2年後ということなので、当時としては、観たくともなかなか観る機会がなかった作品ということになる。よって仁侠映画、実録路線をひと通り観て、自分なりに消化したうえでの鑑賞となったということなのだろう。この作品に関してのインパクトは絶大だったし、深作欣二のベスト5には絶対入れていたほどに好きな作品だった。
面白いことに角川の超大作『復活の日』の観た直後にこの映画をもう一度見直しているあたりに、当時の大作主義化してしまった深作映画に対する私の複雑な思いが伺え、自分でも笑ってしまう。
プロデューサーの俊藤浩滋がこれを観て「お前なぁ、いくらなんでも日本は法治国家だぜ」ともらしたというエピソードがある通り、前作が仁侠映画のドラマツゥルギーへの破壊と、『軍旗はためく下で』が良質な反戦映画というお墨付きへの反発として結実されたのに対して、この映画はフッ切ったように文太の暴れっぷりだけで1本の作品を作ってしまったという、個人映画の様相を呈している。
だから背景となる2大組織の確執は前作通りとしても、描写は一気に単純化して安藤昇のような理解者もいなければ、関西の巨大組織も出てこない。全編、文太が人を殺し、女を犯し、脅し、逃げ、怒鳴り散らし、最後はズタ袋のようになぶり殺されて映画は終了する。
文太がなぶり殺されるのは同じでも、前作にあるようなアイロニーのかけらもない。変な言い方だが「お疲れさん」と労をねぎらいたくなるような気分になってしまうのだ。それほどこの主人公のバイタリティとテンションにはイケイケの陽気さがあった。
今まで深作仁侠映画でさんざん鶴田浩二にガマンを強いてきた渡辺文雄と内田朝雄の2人の親分が、まったくガマンということを知らない文太に翻弄されていく痛快さもカタルシス満点で、観客の破壊願望を刺激して止まない展開となっている。
実はこの時すでに深作も脚本の神波も石川力夫を射程に入れていたらしい。『仁義の墓場』のあの病的なまでのネガティブな狂気の発露は、『狂犬三兄弟』のリアクションなしには到達できなかった領域だったのだと思う。
2003.5.26(月)三百人劇場
忠臣蔵外伝・四谷怪談
1994松竹/脚本:吉田求/深作欣二/出演:佐藤浩市/高岡早紀/津川雅彦/渡瀬恒彦/荻野目慶子/渡辺えり子/石橋蓮司/蟹江敬三/火野正平/田村高廣/真田広之

かつて新解釈による忠臣蔵が撮りたいと意気込む深作と、忠臣蔵は忠臣蔵でなければならないという萬屋錦之介の意見が真っ向から対立し、何やらその折衷案のような忠臣蔵映画『赤穂城断絶』が生まれた。
そのあたりの事情はさすがにリアルタイムで知っていたのだが、深作が16年もの間、そのことにこだわっていたのは少し意外だった。仁侠映画のルーティンをあれだけ嫌っていた深作にとって忠臣蔵という題材が魅力的なものだとは思えなかったからだ。
もっとも『赤穂城断絶』の時から、忠義から落ちこぼれてしまった浪士たちの心情のドラマを追求したいと言っていたので、忠臣蔵そのものよりも、ドラマとしての権威に挑戦してみたかったのだろうとは思う。そこで深作が選んだのは『忠臣蔵』と『四谷怪談』という映画や芝居の定番中の定番を合体させるという試みだった。
もともと鶴屋南北の原作には民谷伊右衛門は赤穂浪士だったという件りがあるらしく、かろうじてこの元禄時代の2大物語を結びつける必然性はなくはないのだが、当然、松竹としてはかなりの反対もあったという。それでも製作にまでこぎつけられたのは、90年代には深作欣二の名前が如何に大きくなっていたのかが伺えるだろう。
さて、この作品はビデオでは観ていたのだが、スクリーンでは今日が所見となった。
いきなりオルフの「カネミナ・ブラーナ」が荘厳に鳴り響くタイトルバックから映画は異様なテンションで進行していく。そして全編に渡ってマーラーの交響曲や琵琶の音色、義太夫が鳴りやまない中で、かなり作り込んだ極彩色の映像が展開していく。
傍線が『忠臣蔵』と『四谷怪談』なのだから様式美の世界ではあるのだが、それにしてもこの映像と音の氾濫は、役者たちの狂気じみたテンションと併せて、ちょっと異常なものを感じた。異常といえば、お岩のもつ薄倖なイメージに反し、健康そのものといった高岡早紀の肢体を見せていくという演出は、あらかじめ観客を怖がらせることを放棄しているようでもあり、吉良邸討ち入りの場面もお岩や民谷伊右衛門の亡霊に見守られていては『忠臣蔵』のカタルシスを望めといっても無理があるだろう。
また蟹江敬三の清水一学、荻野目慶子の梅、渡辺えり子の槇、石橋蓮司の伊藤喜兵衛といった面々が白塗り姿で異形のものとして描かれ、とくに民谷伊右衛門が岩と浪士を裏切り、さらに岩の亡霊によって乱心する吉良屋敷の場面は、観ている方が茫然になるほど百花繚乱たる様式美で、まるで歌舞伎の一幕物を観ているような気分となった。
つまり深作は『忠臣蔵』と『四谷怪談』を合体させながらも、娯楽映画としての見せ場を相殺したうえで、違う地平を目指したのだと思う。ではこれは芸術映画かというとそれも違う。そもそもお岩が赤穂浪士に加勢して清水一学を葬る映画など娯楽映画以外のなにものでもない(笑)。
どうもこの映画は深作が提示した画面の異形さに感想というよりも印象を羅列しただけになってしまった。しかし観終わった後の圧倒感だけはここに強調しておきたい。
2003.5.27(火)三百人劇場
いつかギラギラする日
1992松竹/脚本:丸山昇一/出演:萩原健一/木村一八/荻野目慶子/千葉真一/多岐川裕美/石橋蓮司/原田芳雄/樹木希林/安岡力也/八名信夫/六平直政

この作品のビデオを、ひとり閉店後の店舗で観た。実際、あの頃は仕事に追われていて、劇場に出掛ける気にはなれなかった。今思えば24時間働きづめだったわけではないので、映画館くらいはいつでも行けたのだと思うが、90年代丸々で下手をすれば全盛期の2ヶ月分しか観ていなかった。その意味ではこの1ヶ月間は原点帰りの至福を満喫しているような毎日だ。
そして『いつかギラギラする日』を改めてスクリーンで観て、やはり封切りの時にいくべきだったと思った。逆にいえばビデオでなど観なければ良かったとも思った。
深作は自身のフィルモグラフィと、その時々に映画界が置かれていた状況が妙にシンクロするという作家だっただけに、リアルタイムで観なければ、その意義の大半は喪失する。
おそらくこの1992年という状況は、この年のベストワンが周防正行の『シコふんじゃった。」だったことに象徴されるように日本映画から単純明快なアクション映画が殆どなくなっていた時期だったと思う。要するに娯楽映画の王道と呼ばれていたものが、崩壊寸前のブロックブッキング体制の中でVシネマに収拾されていくのが止めようもなく、さらに洋画のアクション映画がかつてないほどのクォリティで映画街を席巻していた時期でもある。
『いつかギラギラする日』はB級テイスト満点のギャング映画だ。単純に考えたら全国公開するのは二の足も三の足も踏みたいところだっただろう。
結局、これが実現した影には80年代の角川春樹に次いで風雲児となった奥山和由というプロデューサーの出現が大きかった。実際、深作の大ファンだったという奥山でなければ、この環境の中で深作でギャング映画を撮りたいという発想はなかったに違いない。その頃の深作は“金がかかり過ぎて、スケジュールの調整さえままならない監督”というレッテルが貼られていたからだ。奥山の強引ともいえる映画製作者としての手腕があって初めて実現した作品だろう。
この作品はこの年のキネマ旬報ベストテンで7位にランキングされている。おそらく深作欣二の名前でランクインしたのだろう。テイストは『資金源強奪』と『暴走パニック・大激突!』を足したような、お世辞にも社会への告発もなければ、批判もない本当の意味でのアクション映画であって、とてもベストテン作品の類ではない。唯一、妙な言い回しをすれば『資金源強奪』が娯楽映画ならば、『いつかギラギラする日』はエンタティメントという言い方が出来るかも知れない。
冒頭、数人の男が銃に弾丸を装填するシーンから始まるあたりは松田優作作品でも見せた丸山昇一の得意とするスタイリッシュな導入部なのだが、それ以降は銃撃、爆破、カーチェイスがオンパレードする100%深作パワーの押しで全編が貫かれている。
丸山としては、もう少し大人と若者の対決軸で話しを持っていこうとしたらしいが、完成した映画を観ると、最後は金に目を血走らせた人間たちの後先構わない破壊衝動が炸裂して終わったという印象が残る。思えば70年代の後半から80年代まで深作信者が夢想して止まなかった映画であり、これはそんな信者たちに届けられた深作からのプレゼントだったのかも知れない。
あまりにもプレゼントの中身が“いかにも”だったので照れてしまうような映画ではあるのだが。
2003.5.27(火)三百人劇場
おもちゃ
1999東映/脚本:新藤兼人/出演:宮本真希/富司純子/南果穂/喜多川舞/魏涼子/津川雅彦/岡田茉莉子/三谷昇/野川由美子/加藤武/六平直政

三百人劇場でこの特集があると知り、よしゃ!未見の深作は全部観るぞと意気込んだのだが、ここにきて『白昼の無頼漢』『カミカゼ野郎・真昼の決斗』の上映が終了してしまった。それとは別に上映ラインアップ表を観て90年代の3本については迷った。前述したようにこの3本はスクリーンでこそ未見だがビデオでは既に観ていたからだ。
常日頃から「ビデオで観たら、その作品を観たうちには入らない」などと暴言を吐いている手前、その3本はあくまでも未見の作品になるが、なにせ1本ごとに別料金なので無収入者にはかなりの負担となってしまう。
とりわけこの『おもちゃ』に関しては最後まで迷った。ビデオで観たのがひと月前、しかも、この作品に対して深作欣二が監督する必然性がよくわからなかったのだ。聞けば、この作品はライジングプロが宝塚から発掘した宮本真希を売り出すために作られた映画らしい。深作ともあろう大監督がなぜそんな企画にという思いもあった。
映画は、藤乃屋という芸者の仕込屋で下働きをしている主人公のチビが、舞妓になるまでの成長物語を、藤乃屋の人間模様と、京都の風俗を織り込みながら実に淡々と描いている。
過去の『忠臣蔵外伝・四谷怪談』の作風を考えれば、芸者の話を深作が描くとなれば、宮尾登美子の原作ものにありがちな極彩色の画に、愛憎入り乱れる人間群像を想像するに違いない。そういう映画ではありませんとばかり ♪蝶々〜、蝶々〜で始まるタイトルで肩透かしを食らわせるのだが、この作品には悲惨な状況はあっても、悲惨な描写はまったくといいほど出てこない。お定まりの芸者同士のいざこざや旦那衆との愁嘆場も用意はされているが、どちらかというとポジティブに決着させていく。
富司純子扮する女将のおさとも、妻子ある男に入れ揚げた末に金を持ち逃げされる姉に対し「しょうもないなぁ」とため息をつき、姉に扮した野川由美子も「だけどあの人、知らない土地で大丈夫やろか」と案じてみせる。そのおさとも心ならずも金のために三谷昇に体を預けるが、その場面は描かれず、汚れた体を湯に沈めながら「お茶漬けたべたいなぁ」と呟くのみ(富司純子の名演技で屈指の名場面となる)。そもそも成長物語とはいえ、ヒロインは貧しい実家を助けるために借金で売られた身であり、花街に沈んでいく運命なのである。
悲惨な状況を悲惨に描写することに嬉々としていた感のある深作が何故ここまで緩く、淡々と進行させたのかいう疑問は、しかしこの作品を撮っていた時点で深作が自分の病状と余命を把握していたことと、結果として最後の京都撮影所作品になったのを思い出して慄然とした。
もしかすると深作はここで描きたかったのは、自分が馴染んだ京都という街と人々そのものだったのではないか。そういえば、モノクロで映された京の街をチビが駈けていくシーンから始まり、とにかくこのヒロインは京都を走っていく。
最後の神々しいまでの水揚げの場面はビデオでは冗長に感じたが、映画界にデビューした新人女優に、自分の境遇を察していた深作が文字通り水揚げして見せたのではないだろうか。藤乃屋でのお祝いの宴会が何故か心を打つのも納得できる。
2003.6.2(月)三百人劇場
風来坊探偵・赤い谷の惨劇
1961ニュー東映/脚本:松原佳成/神波史男/出演:千葉真一/曽根晴美/北原しげみ/小林裕子/故里やよい/関山耕司/宇佐見淳也/安藤三男/神田隆/久地明
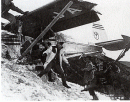
深作欣二を追いかけて四半世紀。ついに監督デビュー作に辿り着いた。製作が1961年ということで、深作の監督としてのキャリアが私の生まれ年から始まったということを改めて知った。(だからどうだってわけではないが…。)
確か映画産業のピークは昭和30年代の前半だったと思うが、この昭和36年当時とても急激な落ち込み傾向はあったとしても、まだ興行形態に対し供給が手一杯だったことは想像できる。そこで東映は第二東映という添えもの専門の早撮り・低予算専門の製作部門を立ち上げて量産体制を堅持していく。今でいうVシネマのようなものだろう。
第2東映はニュー東映と名称を変え、わが深作はその早撮り・低予算のニュー東映からのデビューとなり、この『風来坊探偵・赤い谷の惨劇』は上映時間1時間のSP映画(ショートピクチャー)となった。
よく深作を紹介する記事で、「誰も注目しないニュー東映のSP映画で、ひっそりとデビューをした深作は〜」という論調をよく目にした。当時の量産体制とはそんなものなのだろう。ただしその中でも“第一回監督作品”とポスターに書かれずとも、プロデューサーが勝負の企画を用意して鳴り物入りで新人をデビューさせることがなかったわけではない。
深作の若干後輩になる中島貞夫、佐藤純彌、降旗康男たちの監督デビューと比べると、どちらかというと、どさくさ紛れにという感じがしないでもない。おそらく日芸出身の深作に対し、他の3人が東大卒のエリートだったこともあるのかも知れない。事実、名匠・今井正は東映の屋台骨を背負っていくのは佐藤純彌だと思っていたらしく、後年の深作の昂揚は相当に意外だったらしい。事実、吉田達プロデューサーにいわせれば、佐藤純彌をA級に、深作は完全にB級ラインに乗っていたという(佐藤純彌の実績も凄いとは思うが…)。
今年の1月に深作監督が逝去して以来、監督プロフィールや追悼記事で、このデビュー作品についても語られることが多くなり、いくつかの評論も目にとまるようになった。おそらく『風来坊探偵・赤い谷の惨劇』という貸本のタイトルのようなこの作品が、ここまで注目されたのは42年後にして初めてだったのではないだろうか。
かつて『スター・ウォーズ』の全米大ヒットに際し、試写を見た東映のプロデューサーが公開の2ヶ月前に『宇宙からのメッセージ』を封切ってしまったことを、評論家の山根貞雄が「メンツに関わるとか思わなかったのですか?」と深作に聞いていた時、「ぜんぜん(笑)。もともと日本映画なんてアメリカやフランスやイタリア映画のパクリだからね」と述懐している。
深作のフィルモグラフィを眺めて見ると殆どのジャンル映画を網羅していることがわかるが、この節操のなさは、案外このデビュー作からして日活無国籍アクションのパクリを会社側から押しつけられたことにも起因しているのかも知れない。
東映本体の波が岩に砕けるマークに対して、火山が爆発するニュー東映のマークにも驚いたが、それに続いてセスナが断崖に激突する特撮から始まったのにはもっと驚いた。ひと目で特撮とわかるチャチなものだったが、深作映画の記念すべきファーストシークエンスは何とこんな映像から始まったわけだ。
後は、そこまで真似るかと言いたくなるほどディティールから音楽まで完全に小林旭の『渡り鳥』シリーズと同じ。千葉真一扮する私立探偵・西園寺五郎に対するライバルが“エースのジョー”ならぬ曽根晴美の“スペードの鉄”。スペードの鉄は悪党側の用心棒として登場するが、その悪辣ぶりに雇い主を裏切って、決着をつける時まで五郎と共闘するというという設定まで類似させている。
評論に見かけた「デビュー作からして、すでに深作イズムの萌芽は見てとれる」などという好意的な論調は、大概が追悼に向けての提灯記事だといってもいい。
しかし一方で、これが後にサニ千葉としてアメリカに乗り込むまでとなった千葉真一の主役デビュー作でもあるという側面は見逃すことは出来ない。
おそらく企画段階で新人監督とニューフェイスで60分で2本やらすか程度の軽いものだったのだろうが、この2人が後に日本のアクション映画の旗手として、ジョン・ウーやクェンティン・タランティーノなどの海外の作り手たちからもリスペクトされる存在となっていくのだから不思議な感慨が湧いてくる。
深作映画の主役といえば、鶴田浩二、菅原文太、松坂慶子の名前が浮かぶが、実はデビュー作をともに飾った千葉真一こそが、『仁義なき戦い・広島死闘篇』を経て深作映画のジャンルの変節に関わってきた重要な存在で、千葉は深作を師と仰ぎ、実はタランティーノとのコラボレーションまで企画していた程だという。追悼にあたっての深作健太へのコメントもなかなか泣かせるものがあった。
2003.6.2(月)三百人劇場
風来坊探偵・岬を渡る黒い風
1961ニュー東映/脚本:松原佳成/神波史男/出演:千葉真一/曽根晴美/北原しげみ/小林裕子/故里やよい/関山耕司/宇佐見淳也/安藤三男/神田隆/久地明

それにしても資料によると『風来坊探偵・赤い谷の惨劇』が昭和36年の6月9日公開。続編の『岬を渡る黒い風』が6月23日というのだから笑ってしまう。
つまりデビューしてから12日後には第二作が公開されたことになる。今では考えられないような製作・興行形態だが、早い話しが2本同時撮りをしたわけだが、長尺のストーリーを一気に撮るVシネマよりも連続TVドラマのパターンに近いとはいえ、千葉真一の西園寺五郎を除いてストーリーも設定もロケ地も違う二つの話しを同時に撮るというのも、それなりに難しいのではないか。
事実、深作の監督としての初仕事は二作目の方の西園寺五郎・探偵事務所の場面だったという。
ただ、当然のことながら役名こそ違うものの2作とも出演者が全員同じという珍妙な2本立て体験をした。(曽根晴美は“ジョーカーの鉄”になっていた。)
ここまで書いてきて、それではこの連作は箸にも棒にもかからない駄作なのか?といったら、実はそんなこともない。「深作イズムの萌芽」云々は別にしても、少なくともアクション映画としてのキレは、42年前にしてはという但し書きがつくとしても、十分に鑑賞に堪えるものではあったし、東映のカラーではないという恨みは残ったが、銃撃戦の果てにダイナマイト戦まで発展させる過剰なアクション志向は微笑ましいまでに深作欣二そのものではあった。
ここから42年。紆余曲折を繰り返して深作は60本のフィルムを積み重ねていったのである。
2003.6.3(火)三百人劇場
ファンキーハットの快男児
1961ニュー東映/脚本:田邊虎雄/池田雄一/出演:千葉真一/中原ひとみ/波島進/花沢徳衛/八代万智子/岡本四郎/十朱久雄/加藤嘉/潮健児/岩城力也
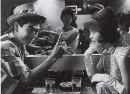
“風来坊”やら“快男児”やらとレトロなタイトルが続くが、早撮り・低予算のニュー東映SP映画第2弾『ファンキーハットの快男児』がもしデビュー作であったとしたら、深作欣二の出発点として強烈な存在になっていたのではないかと思った。
とにかく画面からほと走る溌剌とした若さと熱気には目を瞠った。前作で小林旭の模倣をやらされて窮屈そうだった千葉真一も、ガールハントに夢中なC調やんちゃ坊主・天下一郎というキャラクターを実にのびのびと演じている。
国産省の局長の娘が誘拐された。依頼を受けた天下探偵事務所は張り込むが、犯人に裏をかかれ身代金を強奪されてしまう。そのとき事件に首を突っ込んだ天下のドラ息子・一郎と、投資マニアのみどりは、産業会館建設の利権と株式操作の裏を知り追跡を開始する…。
本来なら90分あってもいいストーリーを60分に凝縮させ、アクションもきっちりと見せるという作りなので、場面展開にタメがない恨みは残ったものの、その分無類のスピード感を獲得した。
『風来坊探偵』の頁で否定した「〜すでに深作イズムの萌芽は見てとれる。」という批評が、もし『ファンキーハットの快男児』に対してのものであれば異論はないと思った。
深作はかつて千葉真一に「アクションはジャズで行け」とアドバイスをしたという。とにかくリズムとテンポで観客を引っ張っていけということなのだが、阪本順治は昔、NHKのドキュメンタリーで『県警対組織暴力』の撮影現場が紹介され時、演出中の深作がさかんに口を動かしてリズムを刻んでいたのを見て感心したという。 『ファンキーハットの快男児』では、三保敬太郎の叩きつけるようなジャズが全編に響き渡る。登場人物たちのセリフ回しが早口なのは、理由はわからないがこの時期の映画の特徴だとしても、この作品はジャズのBGMに登場人物たちが、次へ次へと追い立てられるかのように物語を転がしていく。
またデビュー作『風来坊探偵』は、個人的に生まれ年の映画だったにもかかわらず『渡り鳥』のパクリでローカルアクションになっていたのが不満だったのだが、この映画では1961年当時の都会の街並みや、ちょっとした文化風俗まで見せてくれたことは有り難かった。とくに渋谷は『ギャング同盟』『狼と豚と人間』等でも登場し、初期作品のちょっとした深作フィールドだったのかも知れない。とくに主人公の天下一郎が潮健児の“保釈の虎”と繰り広げるカーチェイスは坂道を利用した臨場感たっぷりの出来映えだったし、首都高3号線のために掘られた穴が延々と続く中での殴り合いなど、なにか夢のような一時を感じた。また都心郊外だった頃の高井戸の古ぼけた駅舎や木造の横浜駅など背景を見ているだけでも楽しい。
中原ひとみが扮した、株式新聞片手に投資に励むお嬢様という設定も、高度成長の風潮を象徴しているのを通り越してバブルを先取りしているのも凄いというのは言い過ぎか?
ただその株好きのお嬢様を天下一郎がナンパして、そこから誘拐事件として発展して行く展開は実に見事だった。ある意味、脚本のお手本のような映画でもある。
千葉真一の動きにもいよいよ磨きがかかり、鉄棒に飛びついた途端にパンツ一丁となって大車輪を鮮やかに決めてプールに飛び込むショットなど、笑ってしまうほど魔力的な映像なのだが、この映画にはそういった魔法のような映像が少なくない。全体的にヌーベルバーグの影響も感じられ、改めてこの作品がデビュー作であって欲しかったと思う。
もっとも深作はヌーベルバーグではなく、イタイアン・ネオ・リアリズムに影響を受けていたという話しもあり、それもそうかも知れないとも思った。
2003.6.3(火)三百人劇場
ファンキーハットの快男児・二千万円の腕
1961ニュー東映/脚本:田邊虎雄/池田雄一/出演:千葉真一/中原ひとみ/波島進/花沢徳衛/小川守/岡本四郎/十朱久雄/佐藤晟也/潮健児/岩城力也

『二千万円の腕』は、中原ひとみがスポーツ記者という設定に変えられてたが、前回の『風来坊探偵』よりも、シリーズとしての認識が色濃く出た作りになっている。
契約金が二千万にもなると噂される甲子園のヒーロー・川原投手の去就をめぐって、地元有力者や後援会などが背後で暗躍する中、ひとりの医師が死体となって発見され、川原投手も行方不明となる。事件に絡んでしまった天下探偵事務所のドラ息子・一郎は、新聞記者になりすまして川原投手の故郷へと向かった…。
冒頭の甲子園のスタンドに各球団のスカウトたちが注視しているニュース映像は、かなり戯画化されていて思わずツッコミを入れたくなったが、1961年というとドラフト会議施行前なので、こういった甲子園のヒーローをめぐってさぞかし札束が乱れ飛んだのだろう。
その甲子園のヒーローと別展開となった医師の謎の死が巧く天下一郎と女性記者のトライアングルに結びつき、相変わらず脚本は絶好調だ。おそらくこの作品でも、天下探偵事務所や帝都ホテルの場面などは同時撮影だったと思うのだが、個人的に花沢徳衛、太宰久雄、岡本四郎といった面々にそれなりにシリーズ特有の愛着を感じてしまった。
当然『ファンキーハットの快男児』はニュー東映とともに消滅してしまったのだが、もしシリーズ化されていれば5本くらいは付き合ってもいい気分になった。さすがにヒロインは毎回代えて欲しいが、前作では“保釈の虎”今回は暴走タクシー運転手“神風の与三郎”として異彩を放った潮健児のどぎつい演技が回を追うごとにエスカレートしていく趣向も面白いのではないか。もちろん田邊虎雄と池田雄一の脚本コンビが、今回も良かったがゆえの戯言ではあるが…。
主演の千葉は、前回では大車輪を披露したが、今度は干潮の時だけ道が出来るという軍艦島へ、大海原をかき分けるように馬で疾走する。
実は2日続けて、深作の東京撮影所時代の盟友・小松範任監督が観客席にいた。劇場から巣鴨の駅までこの人はやたらと大きな声で喋るので、何となく耳を傾けてしまった。「作さんもあれはないよなぁ』とか「本当は室田も居たんだけど、旅館で酔っぱらって関山耕二と大喧嘩してさぁ、それで東京に帰えされたんだよな」とか。何となく当時の撮影所の熱気というか、雄の集団なればこその青春が伝わる思いがした。
昨日と今日。深作欣二31歳の熱かった日々だ。
2003.6.7(土)三百人劇場
北海の暴れ竜
1966東映/脚本:佐治乾/神波史男/出演:梅宮辰夫/高城丈二/山城新伍/沢彰謙/藤田進/阿部徹/室田日出男/谷隼人/清川虹子/三原葉子/由利徹/水島道太郎

この映画は当初上映予定になかったものの、急遽レイトショーという形で上映が決定した。しかもニュープリントでの上映。こういったイレギュラーは大歓迎したい。
この『北海の暴れ竜』の製作年度は1966年。前後の作品として『カミカゼ野郎・真昼の決斗』と『解散式』がある。
深作のフィルモグラフィを見ると、『狼と豚と人間』の不入りで一年間ホサれるまでの初期作品を最初のピークとすると、66年から68年まではある種スランプの状態にあったのではないかと思う。少なくとも、ただ真っ直ぐに『仁義なき戦い』に向かって研ぎすまされていた訳ではない。
逸話によると、『北海の暴れ竜』を観た俊藤浩滋が、「深作に仁侠映画の撮り方を教えてやる。』といって『解散式』をプロデュースしたという。この映画の上映決定を知って、まず興味が湧いたのは稀代の仁侠映画の大立て者にこう言わしめた根拠だった。
この作品は『君が若者なら』と並ぶほど深作映画として知名度の低い作品ではある。少なくとも必死になって深作を追いかけていた頃に名画座で上映されていた記憶はなく、東映やくざ映画の常打ちで週替わり3本立て上映をしていた新宿昭和館や浅草花月でもかかった記憶はない。
深作ブランドでカラー作品だったにもかかわらず上映されなかったということは、おそらくプリントが消滅していたのだろうし、逆にいえば金を掛けてネガからプリントを起こす必要もなかったのではないかと思う。まったく作家が死んだことによって、蘇ってくるものもあるのだ。
北海道の小さな漁港に大網元だった山形家次男の次郎が久し振りに帰ってきた。次郎は、自分の家が落ちぶれ、漁場を仕切るやくざの芦田一家の言いなりになっているのを知る。
俊藤発言の真意は別として、深作作品中で最も仁侠映画のルーティンに従った作品。物語の骨子が主人公のガマン劇になっていたからだ。主役が梅宮辰夫なので、仁侠映画としてのコクや妙味は薄くなっているが、同じ役を高倉健が演じていれば、雰囲気的には『日本侠客伝』のうちの1本でもいいのかとさえ思った。主人公がやくざ的な心情ではなく、あくまでも漁師としてのイナセが行動原理の中心にあったとするあたりはマキノ雅弘の美意識に近い。
もちろん、『ジャコ萬と鉄』とおそらく同じロケ地で展開される『北海の暴れ竜』の場合は、骨子となるガマン劇には仁侠道のしがらみと美意識によるガマンではなく、相手の隙を伺うといった捲土重来的なものとしてのガマンなので『忠臣蔵』に近く、仁侠映画とは似て非ざるものであり、俊藤発言の根拠がそこにあったのであれば納得してしまう。
こう考えてみると結果的に俊藤浩滋が深作にもたらした影響は限りなく大きい。この映画をきっかけに『解散式』で深作を任侠映画で縛り上げスランプのどん底に突き落としながらも、『人斬り与太』で解放させ、過去の確執から深作を拒否していた笠原和夫を説得させて一気に『仁義なき戦い』まで持っていったのだから面白い。
少なくともこの作品や『解散式』でのタメがあったからこそ『人斬り与太』のハジケ方が実現したのではないかと思う。
2003.6.8(日)三百人劇場
仁義の墓場
1975東映/脚本:神波史男/松田寛夫/出演:渡哲也/梅宮辰夫/多岐川裕美/成田三樹夫/安藤昇/芹明香/山城新伍/ハナ肇/今井健二/室田日出男/三谷昇

とうとう私に束の間のハイティーン・ワールドへと誘ってくれた “三百人劇場・深作欣二追悼特集〜まだピリオドは打てない” も最終日となった。
とりあえずのラスト・ピクチャー・ショーはこの映画をおいて他にない。わが生涯のベストワンであると常日頃から公言する『仁義の墓場』だ。
それにしても、最後に観たのが18年前の新宿昭和館というのだからなんという邂逅だろう。思えば、この映画のパッケージソフトはその間、常に身近にはいた。何度ビデオデッキに入れようかと思った。現存プリント消滅によってスクリーンでは観れないことがわかっていたからだ。
既に当時からフィルムはボロボロの状態であったことは百も承知していた。あの上板東映が閉館上映の予定を変更してしまった時、何となくニュープリント最後の機会が今日のような追悼興行になるのだろうという予感はあった。
そして、ひとり緊張におののく中で、見違えるほど鮮明に生まれ変わった『仁義の墓場』の冒頭が映し出された。
「石川力夫さんの少年時代ってどんな感じだったんですかねぇ…・。」
思えば、ある時期から『仁義の墓場』は私にとって「畏れ」の存在になっていた。高校生の時に浅草で初めて観たときのことは今でも鮮烈に憶えている。観終わった後のあの鈍痛のような眩暈感。息がつまりそうな居心地の悪さ。そして帰りの電車の中で次第に昇華していくあの不思議な感覚。
以来、私はとにかく『仁義の墓場』を観続けた。観るたびごとに新たな発見に出会っては悦に入るという日々を過ごしていた。この日本人的な感性の情動を無視し、あえてカタルシス皆無で貫かれた映画(実は、そんなことはないのだが…)に対して涙で向き合ってしまうことの不思議。そうした矛盾を抱えながらもひたすら18年の歳月を待ち続けていたようだ。
私にとって『仁義の墓場』は“絶対映画”だ。いかなることがあっても、この作品への思いは微動だにしないという意味での“絶対映画”という位置づけなのだが、しかし18年の邂逅にはさすがに一抹の不安もあった。内容的な語り口云々など今更どうのこうではないが、40歳を過ぎた自分の情動が、昔のように映画とシンクロして昇華するまでに至るかという不安だった。この作品は、自分にとってはもうその辺りの域まで入ってしまったのだ。
果たして不安は一掃された。それよりも冒頭のナレーションから終戦直後の新宿から、主人公・石川力夫が最初に親分に牙を剥いて刑務所へ送られるまでの前半部から、メロメロになった。さすがにここまでの思いで『仁義の墓場』と対峙するのは初めての経験だった。
この作品の真骨頂は石川が大阪へ処払いとなり、芹明香のパン助と出会う釜が崎ドヤ街からの後半だというのが一般的で、私も何となく前半部は終戦の混乱で暴れ回る傍若無人のイケイケぶりは、後半へのコントラストとして貴重な時間であるという認識でしか、前半部を捉えていなかったのかも知れない。
しかし、突然の石川の闖入によってストーブが倒れ、多岐川裕美が必死になって焼けた畳を拭くシーン。そして転がる蜜柑。これだけで一気に胸が熱くなる。
18年の邂逅と40を過ぎた自分の情動は、ある意味『仁義の墓場』を“愛おしさ”という別次元の地平へと追い立ててしまったのかもしれない。
2003.7.5(土)ヴァージンシネマズ海老名
バトル・ロワイアルII鎮魂歌【レクイエム】
2003東映/脚本:深作健太/木田紀生/出演:藤原竜也/前田愛/忍城修吾/竹内力/酒井若菜/前田亜希/ビートたけし/三田佳子/千葉真一/津川雅彦/末永遙/加藤夏希

私の生まれ年、昭和36年に監督デビューして42年目の初夏。ついにこの日が来た。深作欣二、遺作の封切り初日。ここで深作欣二に対する万感の思いを綴るのはあえて避けたい。
クランクイン直後に病院へ担ぎ込まれたことは周知の事実。そしてそのまま還らぬ人に…。それもあって、やはりこれを深作欣二作品として認識するには違和感があった。“深作健太第一回監督作品”でも良かったのではないか。もちろん全体の構想からキャステング、リハーサル、ほんの僅かの現場演出と絡んだのだから、名目上は“エグゼクティブ・ディレクター”でも良かった。共同監督に留め、「遺作」と呼ぶべきではなかったように思う。72歳の巨匠の遺作とするか、若干30歳の新人監督デビュー作とするかで、この映画が示唆するものがまるで違ってくる。私は敢えて健太のデビュー作として認識したい。
結論からいえば、上映時間133分はあまりにも長すぎた。深作欣二の持論として「2時間を超える映画にロクなものはない」というのがあり、そのことは皮肉にも自身がフィルモグラフィで証明してきたのだが、残念ながらその撤を愛息もまた踏んでしまったようだ。
それは即ち、構成力の不備という点で表出した。まず教師キタノの娘・シオリを狂言廻しとして、父親の残した一枚の絵から想起される七原秋也と、この新BR法なるものを基準に開始される戦闘と殺戮をストレートに追うべきだったのではないか。映画は途中からシオリ不在のまま青井拓馬の話しとなり、七原秋也の話しとなるたびに映画は一定の地点にリワインドされてしまう。それがあまりにももどかしく、結果的に長さの元凶にもなっている。あのぶ厚い原作と42人の殺し合いを2時間以内に収めきった前作の潔さが正直言って偲ばれた。
しかも、秋也を狂言廻しに群像劇の面白さを描出した前作と比べ、本来の中心となるべき3年B組の生徒たちの描写があまりにも平板だったため、字幕スーパーで死亡者の名前が列記されたところで感慨もなく、とくに秋也率いる“ワイルドセブン”と共闘が成立した時点で、実質ゲームは終了しているのだから、その後の死亡者列記それ自体が意味不明になっている。
そういう意味で『バトル・ロワイアルII鎮魂歌』は失敗作となってしまったが、それでも星3つを献上したのは、深作健太という新人監督が不得要領な中で最後までボルテージを下げずに乗り切った事への賛辞だ。少なくとも親父のデビュー作『風来坊探偵』よりも見るべき点は多い。
画面がチラチラする海辺での戦闘場面と、不必要な手持ちカメラのぶん廻しには閉口したが、竹内力の怪演が奔放に炸裂しまくる戦闘開始直前のテンションや血糊のサービス満点のバイオレンス。それを含めたアクション場面の熱気は十分に伝わってきた。
実際問題、ボロボロの身体にモルヒネを打って撮影に臨んだ深作欣二がこの戦闘の連続を全盛期のボルテージで全うできたとも思いにくく、むしろ監督急逝、息子が跡を継ぐという非常事態にあって、火事場の馬鹿力的なパワーが思わぬ副産物となったようにも思った。
もともとがアホのような設定の映画なので、反戦へのメッセージには興味は湧かなかったが、失敗作であったとしても、どこか愛すべき映画ではあったとは思う。
ページの先頭へ
a:10423 t:5 y:3