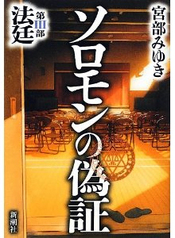◎ソロモンの偽証/第Ⅲ部・法廷
◎ソロモンの偽証
第Ⅲ部 法廷
宮部みゆき
新潮社
この一週間、三冊全2178ページを完走した瞬間、胸に去来したのは「穏やかな感動」と「穏やかな失望」だったか。
一日300ページ単位で読んできたのだからカタルシスは残ったが、『模倣犯』のような衝撃はなく、どちらかといえば『小暮写眞館』のようなちょっと甘酸っぱい成長物語。そのテイストで読むべきだったものを出版社が挟み込んできたリーフレットに結局は煽られてしまったことは否めず、そこに文句のひとつもいいたくなるという読書になってしまった。
しかし間違いなく宮部みゆき『ソロモンの偽証』は2012年読書道ではスティーグ・ラーソンの『ミレニアム』三部作と並ぶエポックメイキングとなりえる作品だった。第一部の時に書いたように、「無我夢中になって小説世界に没頭したい」という目的は十分に完遂されたのではないだろうか。
巻末の初出には「小説新潮」(2009年9月号~2011年11月号)とある。第一部が2002年10月号~2006年7月号だったことを思えば、何たる長い時間を執筆に費やしてきたことか。
もちろん十年間に宮城みゆきも他の連載や書下ろしも抱えていたはずで、本作のみに集中していたわけではなかろうが、構想や取材に割いた時間も半端ではなかっただろうと思うと、『ソロモンの偽証』は膨大な時間と膨大な分量を使って1991年のひと夏の出来事を描いた作品という事実は揺らがない。
【事件の封印が次々と解かれていく。私たちは真実に一歩ずつ近づいているはずだ。けれど、何かがおかしい。とんでもないところへ誘き寄せられているのではないか。もしかしたら、この裁判は最初から全て、仕組まれていた―?そして、最終日。最後の証人を召喚した時、私たちの法廷の、骨組みそのものが瓦解した…。】
執筆期間で興味深いのは『模倣犯』の単行本が2001年の刊行であり、『小暮写眞館』の単行本が2010年の刊行であることだ。宮部みゆき近年史において、その十年を縦断した『ソロモンの偽証』には、第一部と第三部との作風の相違に作家の変遷が見出せるのではないかと思うのは少々穿ちすぎだろうか。
あるいは『ソロモンの偽証』の継続によって『模倣犯』が『小暮写眞館』へと変革していったということはないだろうか。
宮部みゆきは私と同年代なので、40代という期間をまるまる中学生のひと夏を描きながら、30代を越えようとする段階で執筆に入り、50代に入って完成したことへの心境の変化がこの作品に投影されたのではないかという気がしてならない。
何故ならば2002年の段階では、「神戸連続児童殺傷事件」(通称・酒鬼薔薇事件)の余韻がまだ世間に燻っており、あたかも「14歳・中学生」がキーワードのように同世代の犯罪事件が相次いで報道されていた時期にあたるからだ。
あの事件は精神異常者の稀有な犯罪事件ではあったが、「透明な存在であるボクを造り出した義務教育と義務教育を生み出した社会への復讐も忘れてはいない」と、神戸新聞に送りつけられた犯行文も相俟って「14歳・中学生」は何やら不可解な怪物の象徴であるかのように世間を震撼させていたことをよく憶えている。
そして「透明な存在」「義務教育への復讐」というワードが『ソロモンの偽証』でも色濃く影響していることも見逃してはならないと思うのだ。
私は宮部みゆきの代表作と呼ばれるものしか読んでいないのだが、世間を騒然とさせた「14歳・中学生」のキーワードをめぐり、大学教授や評論家、社会学者たちが発言する中で、大人ばかりが評価するのではなく、同世代の子供たち自身の手で真実を明らかにする姿を描いてみたいという意志が『ソロモンの偽証』の執筆へと向かわせたのではないかとも思っている。おそらく彼女はそういうメンタリティの持ち主だ。「14歳・中学生」のキーワードは大人たちではなく、子供たちが真実を見つけ出すのだという思いが、この時間と分量を必要としたのかもしれない。
第三部のページをめくった瞬間から裁判当日の描写になる。そして閉廷を迎える瞬間までのほぼ700ページを藤野涼子の検察側と神原和彦の弁護側との対決に費やされていく。
思えば、第一部の保護者説明会からこの小説は議論の応酬だった。『ソロモンの偽証』はディベート小説の側面を持つが、この第三部の法廷描写はその集大成なのだろう。
『ソロモンの偽証』なるタイトルの意味はずっと気になっていた。
ソロモンは紀元前の古代イスラエルの国王であり、歴史的というより考古学的に知恵者の象徴とされている人物であるらしく、有名な「大岡裁き」の元ネタもソロモンの知恵に由来すると今回初めて知ったのだが、そのソロモンが「偽証」するという、法廷ドラマでありながら既に「偽証」が行われることを前提として、裁判、もとい物語は進行していく。
この物語でいうソロモンとは誰なのか、何ゆえに「偽証」という行為に及ぶのか。そのことは第二部の段階で多くの読者が感づいていたことだったに違いない。私はそこからもうひと捻り転換してみせるのを闇雲に期待してしまっていた。第三部の読書に向かう中で、あくまでもミステリーのロジックに囚われたのは失敗だったと今は思う。
宮部みゆきには『模倣犯』なるタイトルの意味を全体の9割近くまで隠し通してきた“前科”がある。最後の最後で「模倣犯」という言葉で逆転劇を描いて見せた、あのトリッキーなイメージがずっと脳裏をかすめていた。もしかするとこのタイトルも本の帯や差込みリーフレットのコピーもすべてが読者をミスリードしていく仕掛けになっているのではないか。そもそも法廷で陪審員や傍聴人たちの前で衝撃的な真実が明らかになることこそがリーガル・サスペンスの醍醐味というものだろう。
ネタばらしになってしまうので未読の人はこの駄文をこれ以上読まないで欲しいのだが、この小説にはそういったトリッキーな手法は一切用いられることはなかった。
それよりもびっくりするほど虚飾のない無垢な物語としてこの大長編は完結していく。私がこの文の冒頭に「穏やかな感動」と「穏やかな失望」と書いた意味はそういうことだ。
もともと「真実を知るべきだ、知りたい、そうしなければ大人になれない!」という虚飾のない無垢な思いがこの学校内裁判の動機だった。確かに涼子にしてみれば真実は想像を絶するものだったが、読者には想像内のことで物語は終わる。主人公の衝撃に読者が共鳴出来ないという終わり方は物語の解決としては有り得ても、ミステリーの解決としてはどうなのか。
私はこの点で『ソロモンの偽証』を全面的に擁護することは難しいと思っている。
しかし何故、宮部みゆきともあろう作家が、こういう着地を目指したのだろうかと考えると『ソロモンの偽証』の別の側面が見えてくる。
そう、何度も書くようだが、宮部みゆきの主眼がミステリー小説的トリッキーさを目指すのではなく、「14歳・中学生」の真実を、中学生自身が探して、辿り着いていく過程を描くことに傾けられていたということに違いない。目指すものは真相ではなく真実。真実は探して辿り着くものであって、決して暴くものではない。だから衝撃で読者を驚かす必要などなかった。
そのことも読後に痛いほど伝わってきた。
気がつけば、対決するふたりの他にも、弁護人助手を必死の思いで勤めた野田健一。とても中学生とは思えない言動で法廷を仕切った井上康夫・判事。その役割を完璧に貫徹した山崎晋吾・廷吏。検事助手として悪戦苦闘しながら大健闘だった佐々木吾郎と萩尾一美のカップル。そして陪審員たちや証言台に立った中学生たち。
この愛すべき彼らは誰ひとり例外なく(大出俊次や三宅樹理でさえ)、このひと夏を真実に向かって駆け抜けて、成長して見せた。そして五十路を越えたおっさんにはそれが眩しく映った。宮部みゆきの人物造型の本領がいかんなく発揮されたということだろう。
最後の最後に城東三中の学校内裁判が伝説となった2010年の春、教師として三中に赴任する健一の姿が描かれ、そして「もうあの夏は遠い」という一文で幕が下ろされる。
他の生徒たち、いやこの裁判に関わったすべての人たちのその後が気になるところだが、「みんな友達となった」と、健一のひと言で済ませてしまったのは、ノスタルジーに陥らせないためのギリギリの線だったのだろう。そう野田健一もこの物語の重要な主役のひとりだった。
十年前の出来事を描き始めた本作も、終わってみれば二十年前の出来事になっていた。まだその頃は携帯電話も普及していなかったことで成り立つ場面も少なくない。発端は14歳の犯罪事件だったとしても、それは決して過去のことではなく、未だに中学・高校生たちは時代の中で揺れ動いている。
むしろ今のほうが事態は深刻化しているのかもしれないのが何ともやるせないが。
a:6707 t:1 y:0